「HTMLでリンクを作りたいけど、どうやって書けばいいの?」って迷うことありますよね。
さらに、日本語が入ったURLや記号がうまく動かないと、ちょっと困ってしまいます。
今回は、HTMLでURLを正しくリンクに設定する方法や、URLエンコードの基本知識についてわかりやすく解説します。
この記事を読めば、リンク設定のミスを防ぎ、SEOにも強いWebページを作れるようになりますので、ぜひ最後まで参考にしてください。
HTMLでURLをリンクとして設定する基本
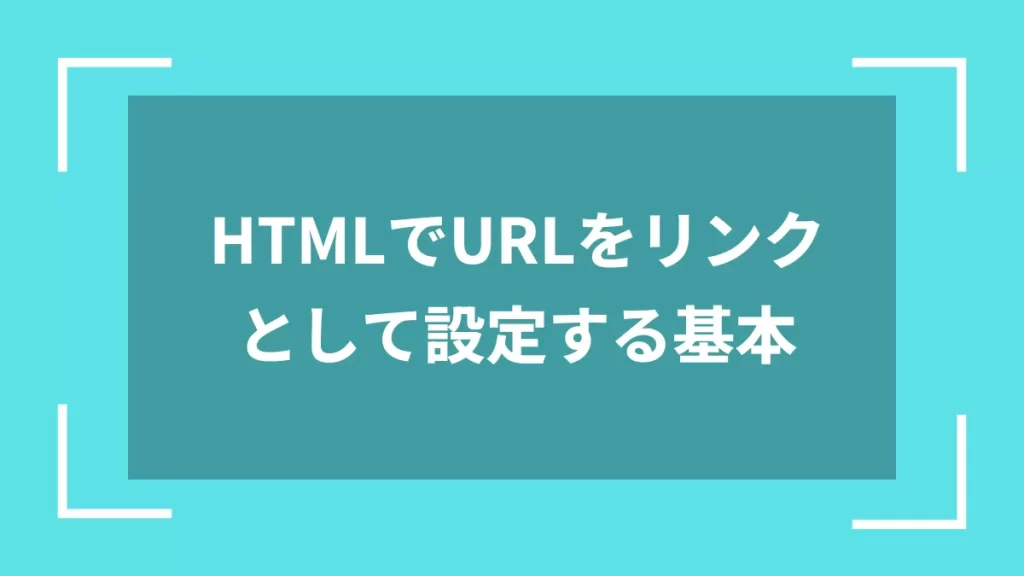
aタグの基本構文と使い方
HTMLでリンクを作るときには、aタグを使います。
このタグは、クリックすると他のページやファイルへ移動できるようにするためのものです。
aタグには、hrefという属性を使ってリンク先のURLを指定します。
<a href="https://example.com">リンクテキスト</a>
このように書くと、「リンクテキスト」と表示される部分をクリックすると「https://example.com」へ移動できます。
aタグの使い方を覚えると、さまざまなページ同士を簡単につなげられるようになります。
<a>タグは「アンカー」と読みますhrefは「ハイパーリンク・リファレンス」の略です- リンクテキストは自由に書き換えられます
- リンク先が正しくないと、クリックしてもエラーになります
- ダブルクオーテーションでURLを囲むのがルールです
HTMLの基本であるaタグの使い方をしっかり覚えておけば、Webページ作成の幅が広がります。
href属性に指定するURLの形式
リンクを正しく動かすためには、href属性に入れるURLの形式を理解することが大切です。
URLにはいくつかの種類があります。
代表的なURL形式には次のようなものがあります。
- https://などから始まる「絶対URL」
- ファイルの場所を表す「相対URL」
- 同じページ内を移動するための「アンカーリンク」
たとえば、別のWebサイトにリンクするなら、https://〜のような完全なURLを使います。
一方で、自分のWebサイト内の他のページにリンクしたいときは、about.htmlのような短い形式でも大丈夫です。
- 絶対URLは他サイトにも使える
- 相対URLは同じサイト内の移動に便利
- アンカーリンクはページ内の特定位置へジャンプできる
リンク先のURLを正しく書くことで、訪問者が迷わずページを移動できます。
絶対パスと相対パスの違い
リンク先の書き方には、絶対パスと相対パスの2つの方法があります。
これらは、どのようにリンク先の場所を指定するかの違いです。
- 絶対パスは「https://example.com/page.html」のようにURL全体を書く
- 相対パスは「./page.html」や「../page.html」のように現在の位置からの移動で書く
絶対パスはリンク先がどこにあっても正確に指定できますが、相対パスは現在のファイルの位置に応じて変わるため、管理がしやすい反面、間違えるとリンク切れになりやすいです。
- 絶対パスは他のサイトや場所を指定するのに便利
- 相対パスは同じドメイン内での移動に使う
- Web開発では相対パスを使う場面が多い
リンク設定を正しくするためには、どちらのパスを使うかしっかり理解して選ぶことが重要です。
リンク先の新しいタブでの開き方
ユーザーがリンクをクリックしたときに、新しいタブで開くようにするには、aタグにtarget="_blank"を追加します。
<a href="https://example.com" target="_blank">こちらをクリック</a>
このように書くと、リンクをクリックしても現在のページはそのままで、新しいタブにリンク先が表示されます。
- target属性は「ターゲット」と読みます
- 新しいタブで開くと、ユーザーが元のページに戻りやすい
- 外部サイトへのリンクによく使われます
- target=”_blank”を使うときはrel属性もセットで使うのが安全です
ユーザーに優しい設計をするためには、新しいタブでのリンク設定を覚えておくと便利です。
アンカータグとリンクの関係
HTMLでいうアンカータグは、リンクの出発点となる部分です。
このaタグの中にリンクのテキストを書いて、href属性でリンク先を指定します。
アンカーという言葉には「つなぐ」意味があり、クリックすることで他の場所へ“つなげる”働きをしています。
- aタグは必ず閉じタグとセットで使う
- リンクテキストは自由に編集できる
- 画像やボタンにもaタグを使ってリンクをつけられる
- HTMLの中ではナビゲーションにも使われる
アンカータグの正しい使い方をマスターすれば、Webページの構成をもっと自由にデザインできます。
HTMLにおけるURLエンコードの基本知識
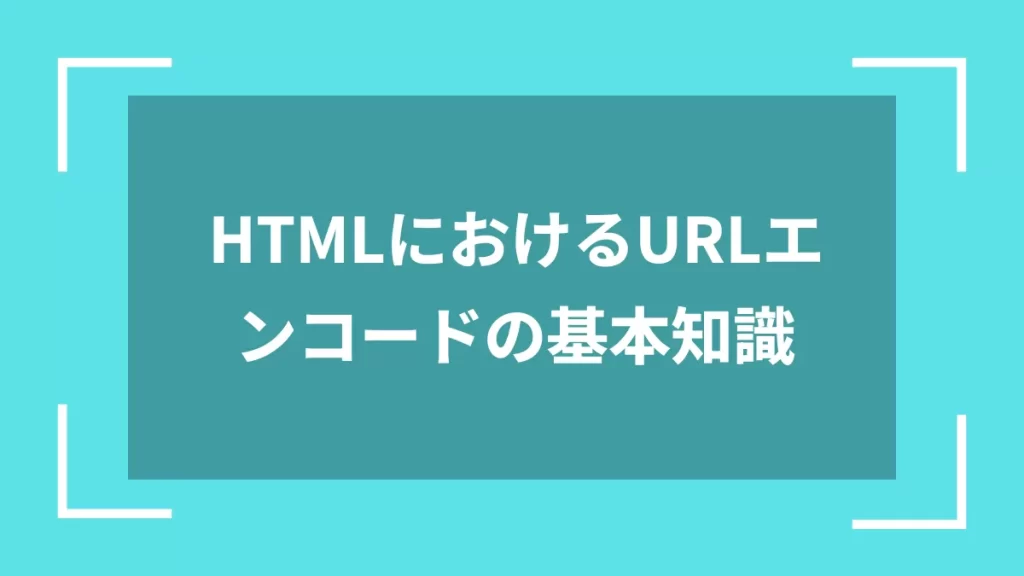
URLエンコードとは何か
URLエンコードとは、Webページで使えない文字や記号を、英数字のコードに変換することです。
Webの仕組みでは、日本語や一部の記号はURLにそのまま使うことができません。
そこで、特別な記号を使って表現し直すのがURLエンコードです。
たとえば、「あ」という文字は%E3%81%82のように変換されます。
これはパソコンやサーバーに正しく伝えるためのルールです。
URLエンコードのことを理解しておくと、ページのリンク先に日本語や記号を含めるときにトラブルを防ぐことができます。
- 使えない文字を安全な記号に変える
- 日本語や記号が含まれるURLで必要になる
- メール送信やフォームでも使われる
- 文字化けを防ぐために重要
URLエンコードを知っていれば、より正確で安全なリンク設定ができます。
なぜURLエンコードが必要なのか
URLに日本語や一部の記号をそのまま使ってしまうと、文字化けやリンクエラーが起こることがあります。
これを防ぐために、URLエンコードが必要になります。
Webブラウザやサーバーは、英数字だけで構成されたデータを正しく読み取ります。
そのため、それ以外の文字は特殊なコードに変換する必要があります。
- 半角スペースは
%20に変換される - 「&」や「?」などの記号は区切り文字として使われるのでエンコードが必要
- 日本語はそのままだとサーバーが理解できない
このように、正しくデータを伝えるために、URLエンコードは欠かせません。
トラブルを避けたいなら、エンコードの役割をきちんと理解しておくことが大切です。
エンコードが必要な文字と理由
URLで使えない文字には、特別な意味を持つ記号や、文字コードの関係で処理できない日本語などがあります。
これらの文字はエンコードしないと、URLが正しく機能しません。
どんな文字がエンコード対象になるのか、次のような例があります。
- 空白(スペース)
- 日本語(例:「東京」)
- 記号(例:「#」「&」「%」など)
これらの文字は、Webの世界ではコマンドの一部とみなされるため、%20や%E6%9D%B1%E4%BA%ACのように変換しておく必要があります。
- 「#」はアンカーとして使われる記号
- 「&」はクエリ文字の区切りに使われる
- 「%」はすでにエンコードに使われている記号
間違ってそのまま使うと、リンクが動かなくなったり予期しないページに飛んだりするので、必ずエンコードを行いましょう。
実際のエンコード方法と例
URLエンコードを実際に行うには、変換ツールやプログラムを使います。
手作業でも可能ですが、間違いやすいため自動で変換する方法が一般的です。
たとえば、JavaScriptではencodeURIComponent()という関数を使うことができます。
encodeURIComponent("こんにちは")
このコードを使うと、結果は%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AFになります。
他にも、以下のような方法でエンコードが可能です。
- オンラインのエンコードツールを使う
- プログラミング言語の関数を使う
- CMSやフォーム設定時に自動エンコードを使う
エンコードされた文字列は一見わかりにくいですが、ブラウザは正確に読み取ることができます。
正しく使うことで、安全でスムーズなページ遷移が可能になります。
日本語URLを使う際の注意点
日本語をURLに使うときは、文字化けや認識エラーを防ぐために、必ずエンコードする必要があります。
日本語はそのままではWebサーバーが読み取れないため、特殊な記号に変換しなければいけません。
日本語を含むURLは以下のような特徴があります。
- そのままコピーすると正しく貼れないことがある
- メールやSNSで共有するとリンク切れになることがある
- 検索エンジンにはエンコードされた形式で登録される
たとえば、https://example.com/東京というURLは、実際にはhttps://example.com/%E6%9D%B1%E4%BA%ACという形式で処理されます。
日本語をURLに使う場合は、リンクが正しく機能するようにエンコード処理を忘れずに行うようにしましょう。
エンコードによるSEOへの影響
URLエンコードはSEOにも関係があります。
正しくエンコードされていないURLは、検索エンジンが正しく認識できず、評価が下がる原因になります。
Googleなどの検索エンジンは、エンコードされたURLを問題なく読み取りますが、複雑すぎるURLや意味がわかりにくいURLは避けた方が良いとされています。
SEOにおけるポイントをまとめると次の通りです。
- URLはなるべく短くわかりやすくする
- 日本語URLはエンコード後の見た目が長くなるため注意
- リンクが壊れないようにエンコードは必須
- 意味のある英単語を使うことでSEO効果が高まる
エンコードを適切に行いながら、検索されやすく、クリックされやすいURL設計を心がけることが大切です。
デコードとの違いと使い分け
URLエンコードの反対はURLデコードです。
これは、変換された記号を元の文字に戻すことを意味します。
エンコードされたURLを読みやすくするために使います。
たとえば、%E6%9D%B1%E4%BA%ACというコードをデコードすると「東京」になります。
このように、エンコードとデコードはセットで使うことが多いです。
- エンコードは「変換する」
- デコードは「元に戻す」
- JavaScriptでは
decodeURIComponent()を使う - ユーザーに表示するときはデコードが必要になることもある
どちらもWeb制作でよく使われる処理なので、違いをしっかり理解して正しく使い分けましょう。
リンク設定でよくあるミスとその回避法
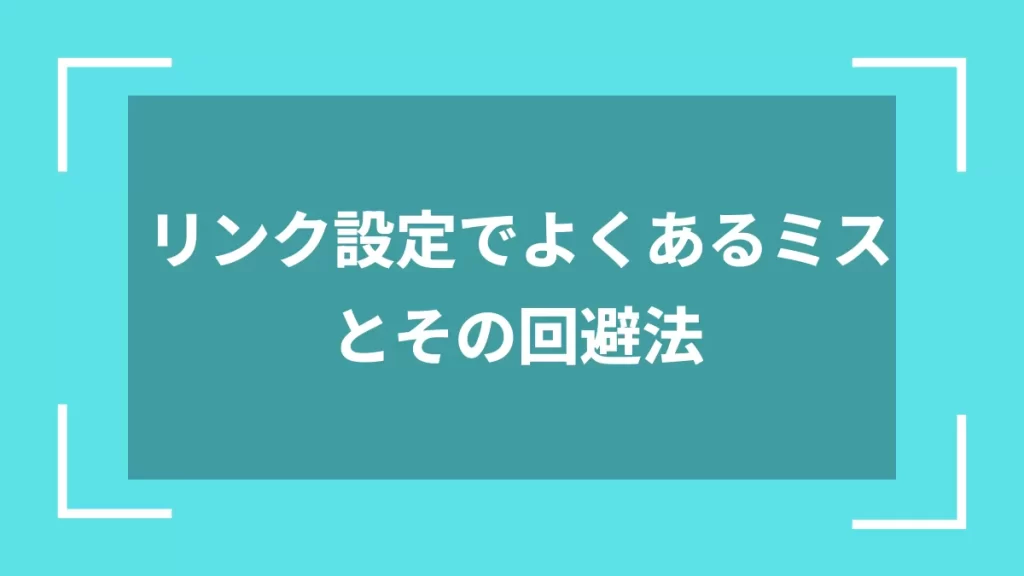
リンク切れを防ぐためのチェックポイント
リンクが正しく動かない「リンク切れ」は、ユーザーの離脱を招く大きな原因です。
リンク切れを防ぐためには、事前のチェックと定期的な確認がとても大切です。
特に外部サイトへのリンクや、削除されたページへのリンクは注意が必要です。
リンク切れを防ぐためのチェックポイントを紹介します。
- リンク先のページが存在するか確認する
- 相対パスが正しく指定されているか確認する
- 外部リンクが正しいURLに向いているか確認する
- リンク先がリダイレクトされていないか確認する
- リンク文字列と実際のURLが一致しているか確認する
リンクを設置したあとも、定期的にリンク先の状態を見直すことで、ユーザーにとって快適なサイトを保てます。
相対パスの設定ミスによるトラブル
リンク先のURLを相対パスで指定する場合、階層の違いや記述ミスが原因で正しく動かないことがあります。
特にフォルダの深さが異なるページ間でリンクを張るときは注意が必要です。
以下は、相対パスでよくあるミスと注意点です。
- 現在のファイルの位置を把握していない
- 「../」を使いすぎて階層を誤る
- 拡張子が抜けていて読み込まれない
- 大文字と小文字の違いによるリンクエラー
たとえば、現在のHTMLファイルが/site/page/index.htmlにあるとき、../contact.htmlと書くと/site/contact.htmlを参照することになります。
位置関係を間違えると正しくリンクされません。
正確な相対パスを書くには、ファイルの構成をしっかり理解しておくことが重要です。
リンクの対象が正しく表示されない原因
リンクはあるのに、クリックしても目的のページが開かなかったり、想定外のページに移動してしまうことがあります。
これはリンクの設定ミスが原因で起こります。
このようなミスが起きる原因はさまざまです。
- URLに全角文字が含まれている
- 不正な記号が使われている
- URLの前後に余計なスペースが入っている
- href属性が空になっている
- JavaScriptやCMSの設定と干渉している
正しく表示させるには、リンク先のURLをひとつひとつ丁寧に確認し、動作確認をすることが欠かせません。
誤動作の原因を知っておけば、似たようなトラブルも未然に防げます。
httpとhttpsの混在による問題
最近のWebサイトでは、セキュリティのためにhttpsが主流になっています。
ところが、httpsページの中にhttpリンクが混ざっていると「混在コンテンツ」となり、エラー表示や読み込みブロックが発生することがあります。
httpとhttpsの混在によるトラブルを防ぐために注意すべき点をまとめます。
- 全てのリンクをhttpsに統一する
- 外部リンクでもhttps対応のURLを使う
- 画像やスクリプトの読み込みもhttpsにする
- CMSやテンプレートの自動生成URLを確認する
Google Chromeなどのブラウザでは、混在コンテンツを自動的にブロックする仕様になっているため、すべてのリンク先が安全なhttpsであることを確認しましょう。
同一ページ内リンクの正しい使い方
長いページの中で特定の位置にジャンプさせたいときは、同一ページ内リンク(アンカーリンク)が便利です。
ただし、設定方法を間違えると動作しません。
正しく設定するには、リンク元とリンク先のIDをしっかり対応させる必要があります。
<a href="#section1">この部分へジャンプ</a>
<div id="section1">ジャンプ先の内容</div>
アンカーリンクでの注意点を以下にまとめます。
- id属性の値は重複しないようにする
- 「#」のあとに正確なID名を記述する
- JavaScriptの干渉がないか確認する
アンカーリンクは、ユーザーの使いやすさを高める便利な仕組みなので、正しく設定して活用しましょう。
外部リンク設定時のnofollow属性の使い方
SEOにおいて、nofollow属性はとても重要な役割を持ちます。
外部リンクにこの属性をつけることで、検索エンジンがそのリンク先を評価対象にしないようにできます。
<a href="https://example.com" rel="nofollow">外部サイト</a>
nofollowを使う場面は次のようなケースがあります。
- 信頼性が不明なサイトへのリンク
- 広告やアフィリエイトリンク
- コメント欄にある自動生成リンク
nofollowを適切に使うことで、自分のサイトの評価を守ることができ、検索エンジンにも正しい情報を伝えることができます。
SEO的に避けたいリンク設定のパターン
リンクの設定次第でSEOに悪影響を与えることもあります。
検索エンジンにとって分かりにくいリンクや、不自然なリンク構造は避けるべきです。
以下はSEO的にやってはいけないリンクの例です。
- 「こちら」や「クリック」だけのリンクテキスト
- JavaScriptだけでリンクを作る
- 隠しリンク(見えないリンク)を使う
- 1ページ内に同じリンクを何度も貼る
- リンク先が存在しないページに向いている
検索エンジンはリンクのテキスト内容や配置もチェックしています。
ユーザーにも検索エンジンにもわかりやすく伝えるリンク設計を心がけましょう。
SEOに強いURLリンク設定のベストプラクティス
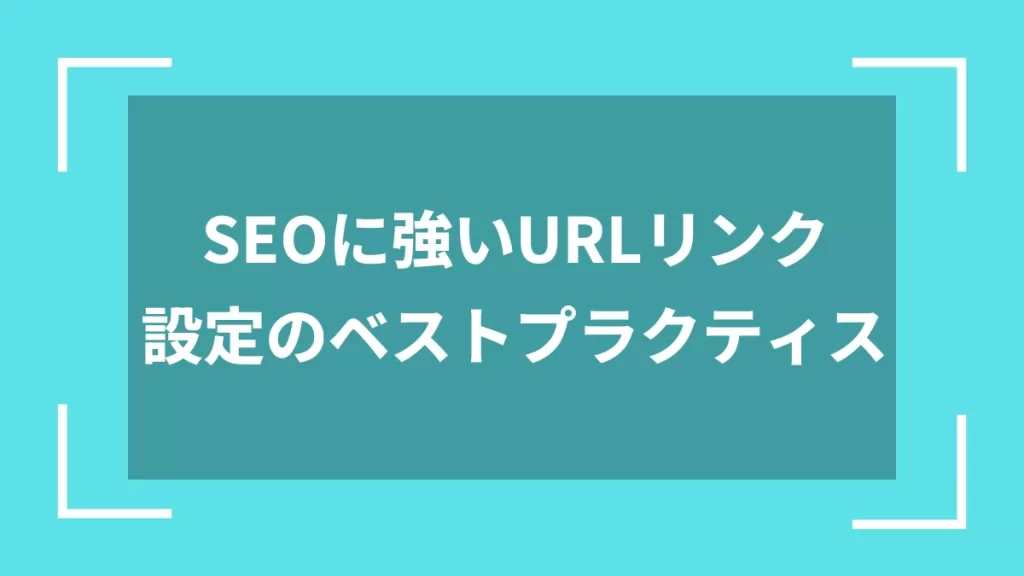
クローラビリティを意識したURL設計
検索エンジンのロボット(クローラー)がサイトを巡回しやすくするために、クローラビリティを意識したURL設計が必要です。
クローラーがURLを正しく読み取れないと、ページが検索結果に表示されにくくなります。
以下のような工夫をすることで、クローラーに優しいURLを作ることができます。
- 意味のある単語をURLに入れる
- 日本語ではなく英単語で表記する
- 短くわかりやすい構成にする
- 「?id=123」のような動的URLは避ける
- スラッシュ(/)で階層を整理する
クローラーがページを正しく理解するためには、URLの構造がシンプルで論理的であることがとても重要です。
リンクテキストの適切な書き方
リンクに使うテキスト(アンカーテキスト)は、リンク先の内容を分かりやすく伝える言葉を使うことがポイントです。
「こちら」や「詳しくはこちら」などの曖昧な表現は、SEOにもユーザーにも良くありません。
良いリンクテキストの特徴をいくつか挙げます。
- リンク先の内容が明確にわかる
- キーワードが含まれている
- 短く簡潔にまとめられている
- 自然な文章の中に組み込まれている
たとえば、「お問い合わせページはこちら」ではなく、<a href="/contact">お問い合わせフォーム</a>のように書くと、ユーザーにも検索エンジンにも伝わりやすくなります。
内部リンク構造の最適化
サイト内のページ同士をつなぐ「内部リンク」は、ページの評価を伝える大切な仕組みです。
適切に設計することで、訪問者も検索エンジンも情報を見つけやすくなります。
内部リンクを最適化するためのポイントを紹介します。
- 重要なページはトップページやメニューからリンクする
- 関連性のあるページ同士をつなぐ
- 1ページからのリンク数を適度にする
- リンク切れや重複を避ける
内部リンクをしっかり設定しておくと、ページ同士のつながりが明確になり、サイト全体の評価アップにもつながります。
パンくずリストによるURL階層の整理
パンくずリストとは、今どのページにいるのかを階層で示すナビゲーションです。
ユーザーが迷わず移動できるだけでなく、検索エンジンにもサイト構造を伝える役割があります。
パンくずリストを使うメリットは次の通りです。
- ユーザーが上位のページに戻りやすい
- サイト全体の構造が明確になる
- 検索結果に表示されることがある
- 内部リンクとしてもSEO効果がある
HTMLでパンくずリストを作るときは、構造化データを追加するとより効果的です。
たとえばschema.orgを使ったマークアップをすることで、Googleの検索結果で強調表示される可能性があります。
canonicalタグとリンクの整合性
同じ内容のページが複数存在する場合、canonicalタグを使って検索エンジンに「正規のURL」を伝えることができます。
これをしないと、重複コンテンツとみなされてSEO評価が分散してしまいます。
canonicalタグの使い方は以下のようになります。
<link rel="canonical" href="https://example.com/page">
このタグをhead要素内に入れることで、検索エンジンに「このページが本物です」と伝えることができます。
- URLの末尾に「/」の有無で別ページ扱いになるのを防げる
- 同じ商品ページを色別で分けるときに使える
- CMSが自動で複数のURLを生成する場合に便利
正規URLを明示することで、評価が集中しやすくなり、検索順位にも良い影響を与えます。
URLの正規化とリダイレクトの活用法
URLの正規化とは、1つの内容に対して1つのURLを割り当てることです。
これをしないと同じページが複数のURLで存在し、評価が分散したり重複扱いになったりします。
正規化の方法には以下のような手段があります。
- canonicalタグで正規URLを指定する
- 301リダイレクトを使ってURLを1つにまとめる
- URLの末尾の「/」の有無を統一する
- 「wwwあり」と「wwwなし」を統一する
また、URLを変更したときや古いURLから新しいページに誘導したいときには、301リダイレクトを使います。
これによりSEO評価を引き継いだままページを移行できます。
モバイル対応とリンク設計の注意点
スマートフォンでWebページを見る人が増えた今、モバイル対応はリンク設計にも重要です。
小さな画面で使いやすくするためには、リンクのサイズや配置にも気を配る必要があります。
モバイル対応でのリンク設計のポイントを紹介します。
- リンクテキストは大きく、タップしやすくする
- ボタンや画像にリンクをつけると便利
- 誤タップを防ぐために間隔をあける
- スマホでの見え方を必ずチェックする
Googleもモバイルフレンドリーなサイトを評価するので、モバイルでの使いやすさはSEOにもつながります。
リンク設定を工夫することで、すべてのユーザーにとって使いやすいサイトが作れます。
まとめ
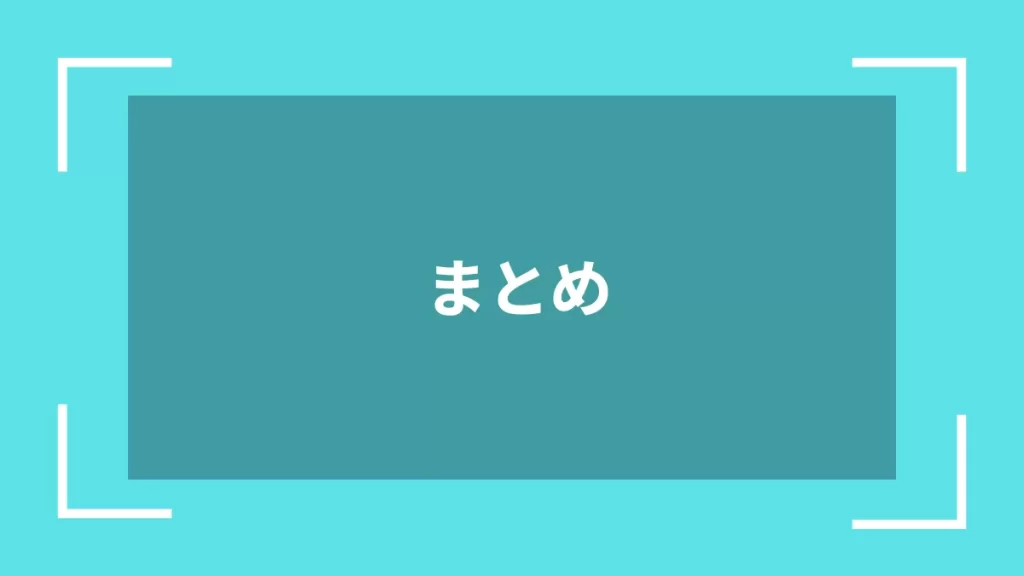
これまでに紹介した「url en HTML」の基本をふまえて、大切なポイントをもう一度おさらいしましょう。
- aタグを使って正しくリンクを作る
- href属性には正確なURLを指定する
- URLエンコードで日本語や記号の文字化けを防ぐ
- リンク切れや相対パスの間違いに気をつける
- SEOに強いリンク構造を意識する
- モバイル対応のリンク設計も忘れずに行う
正しいリンク設定とエンコードの知識を活かして、あなたのWebサイトをもっと見やすく、検索されやすいものにしていきましょう。

















