「たくさんの情報を見せたいけど、ページがごちゃごちゃして困るな…」って思ったことありませんか?
すっきり見せたいけど、全部隠すと見てもらえないし、どうすればいいのか迷いますよね。
そこで今回は、HTMLアコーディオンの作り方と応用例について、わかりやすく解説していきます。
むずかしいコードを使わなくても、シンプルな仕組みで見た目も使い方もスッキリさせることができます。
この記事を読めば、自分のサイトにぴったりなアコーディオンを作れるようになります。
ページをもっと見やすく、使いやすくしたい方は、ぜひ最後まで読んで参考にしてくださいね。
HTMLアコーディオンの基本的な作り方
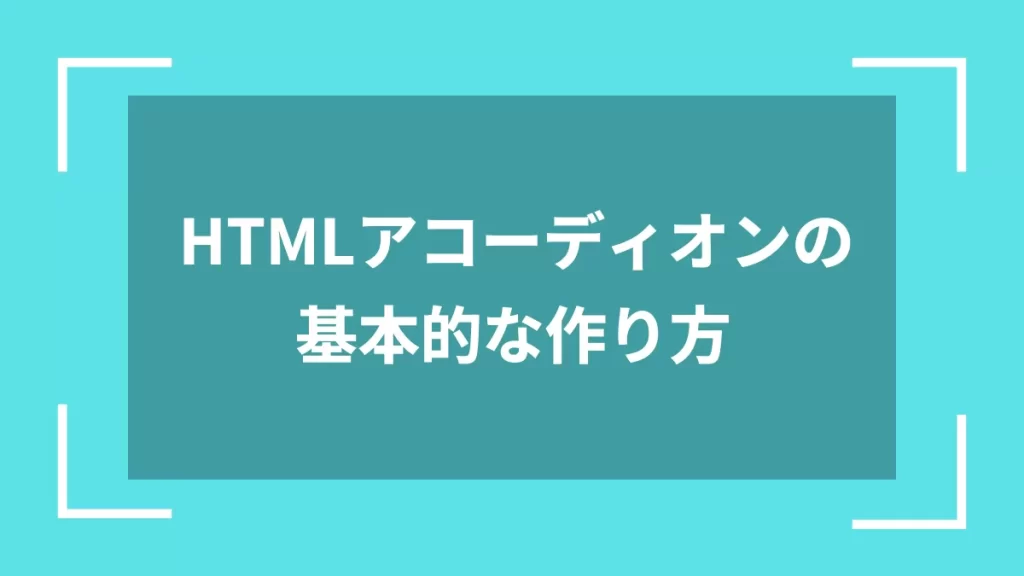
アコーディオンとは何か
アコーディオンとは、クリックやタップによって情報を「開く・閉じる」ことができる仕組みのことをいいます。
ウェブサイトでよく見る「質問をクリックすると答えが表示されるFAQ」や「コンテンツが折りたたまれているメニュー」などが代表的です。
見た目がスッキリしていて、たくさんの情報をコンパクトに見せたいときに便利です。
アコーディオンのポイントは、ユーザーが見たい情報だけを自分で選んで表示できるところにあります。
これによって、読みやすくてストレスのないページになります。
アコーディオンの特徴は以下の通りです。
- クリックやタップで中身が開く
- 一度にたくさんの情報を見せなくて済む
- ページのレイアウトをコンパクトに保てる
- スマホでも使いやすい
- FAQやメニューにピッタリ
このようにアコーディオンは、見た目と使いやすさの両方を考えたデザインの中でとても役立つ要素です。
HTMLとCSSだけで実装する方法
アコーディオンは、実はJavaScriptを使わなくても、HTMLとCSSだけで作ることができます。
これは、特に初心者の方や簡単なページに取り入れたい方におすすめの方法です。
この方法では、主に``と`
以下のような手順で作ります。
- チェックボックスをHTMLで用意する
- ラベルと連動させてクリックできるようにする
- CSSでチェック状態に応じて表示・非表示を切り替える
実際の簡単なコードは以下のようになります。
<input type="checkbox" id="toggle">
<label for="toggle">クリックして開く</label>
<div class="content">ここに内容が入ります</div>
CSSで次のようにスタイルを設定します。
.content {
display: none;
}
#toggle:checked + label + .content {
display: block;
}
このように、HTMLとCSSだけでもシンプルで軽いアコーディオンを作ることができます。
特に動作が早く、読み込みも軽くなるので、ページの速度を大事にしたい場合にぴったりです。
JavaScriptを使った基本構造
HTMLとCSSだけでもできますが、JavaScriptを使うことでより柔軟なアコーディオンが作れます。
たとえば、開いているセクションを自動で閉じたり、アニメーションを付けたりすることができます。
基本的なJavaScriptの構造はとてもシンプルです。
次のような流れで実装します。
- アコーディオンのタイトルにクリックイベントを設定
- クリックされたら中身を表示または非表示に切り替える
- 必要に応じて他の開いているセクションを閉じる
- CSSで表示・非表示を切り替える
以下はシンプルなサンプルコードです。
document.querySelectorAll('.accordion-title').forEach(function(title) {
title.addEventListener('click', function() {
this.classList.toggle('active');
var content = this.nextElementSibling;
if (content.style.display === "block") {
content.style.display = "none";
} else {
content.style.display = "block";
}
});
});
このようにJavaScriptを使うと、よりインタラクティブな動きが可能になります。
複数のアコーディオンを一括で制御したい場合にも向いています。
ラジオボタンやチェックボックスでの実装
JavaScriptを使わずにラジオボタンやチェックボックスを利用する方法も人気です。
この方法はHTMLとCSSだけで作れるため、学習中の方にもおすすめです。
ここではラジオボタンを使うアコーディオンの例を紹介します。
- ラジオボタンで1つだけ開く形式が作れる
- チェックボックスでは複数開閉も可能
- labelタグと連携させてクリックで操作
- CSSで:checked状態に応じて表示
- JavaScript不要で高速に動作
この方法なら表示の切り替えがスムーズで、HTMLに詳しくなくても比較的かんたんに作成できます。
FAQやメニューなどにも応用しやすいので便利です。
よく使われるHTMLタグの解説
アコーディオンを作るときには、いくつかのHTMLタグをよく使います。
それぞれの役割をしっかり理解しておくと、トラブルが起きにくくなります。
ここで使われるタグとその意味を確認しておきましょう。
- <input>:状態の切り替えに使う
- <label>:見出しやクリック対象として使う
- <div>:中身のコンテンツを入れる
- <section>:意味的にまとまりをつけたいときに使う
- <button>:JavaScript操作時に使用されることが多い
これらのタグを組み合わせることで、正しく動くアコーディオンを作ることができます。
HTMLの基本を知ることで、応用もしやすくなります。
コーディング時の注意点
アコーディオンを作るときには、ちょっとしたミスで正しく動かなくなることがあります。
そこで、いくつかの注意点を紹介します。
- HTMLの構造を正しく保つ
- IDとfor属性を正確に対応させる
- CSSセレクタの書き方を間違えない
- JavaScriptは閉じタグの前で読み込む
- デバッグツールを使って確認する
これらを守れば、思った通りに動くアコーディオンが作れるようになります。
失敗を防ぐためにも基本をしっかり押さえましょう。
表示・非表示の切り替え原理
アコーディオンの「開く・閉じる」動作は、要素の表示・非表示を切り替えることで実現しています。
これは、CSSの`display`や`height`、`opacity`などのプロパティを操作することで制御します。
中でも一番シンプルな方法は、次のようなCSSを使う方法です。
.content {
display: none;
}
input:checked + label + .content {
display: block;
}
このように、状態に応じてCSSのプロパティを変更することで、クリックで内容を見せるしくみができあがります。
基本のしくみを理解すると、さまざまな応用もやりやすくなります。
シンプルで使いやすいアコーディオンのデザイン例
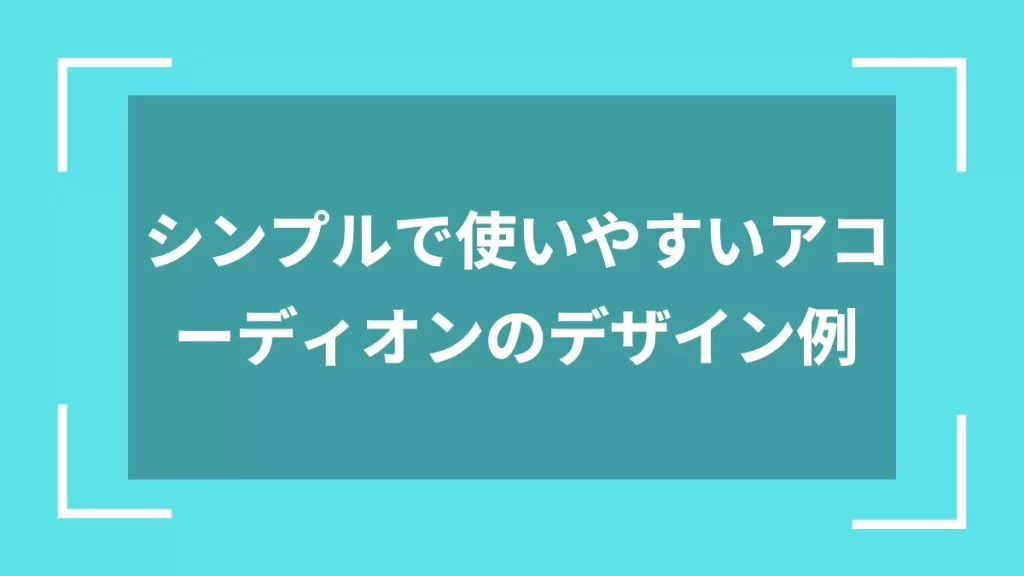
ミニマルなスタイルの実装例
アコーディオンを作るとき、シンプルなデザインはとても人気があります。
余計な装飾をせず、中身に集中できるデザインはユーザーにとっても見やすく、操作がしやすくなります。
ここではミニマルデザインのアコーディオンを作るコツを紹介します。
以下のポイントを意識することで、洗練されたアコーディオンに仕上がります。
- 背景は白や薄いグレーなど目に優しい色にする
- 枠線や影を使いすぎない
- 見出しの文字サイズは大きめに、本文は読みやすい大きさにする
- 開閉のアイコンはシンプルな矢印やプラスマークにする
- 余白をしっかり取って窮屈に見せない
このように最小限の要素で作ることで、どんなサイトにもなじみやすいアコーディオンになります。
特にスマホ表示でも見やすくなるのでおすすめです。
レスポンシブ対応の方法
アコーディオンをスマホやタブレットでもきれいに表示させるにはレスポンシブ対応が必要です。
画面の大きさに合わせてデザインやレイアウトを変えることで、どのデバイスでも快適に使えるようになります。
レスポンシブ対応の主な方法は以下の通りです。
- 幅を%(パーセント)で指定して伸縮させる
- メディアクエリで画面サイズに合わせたスタイルを設定
- 文字サイズや余白を相対値(emやrem)で指定
- 表示が崩れたときのために折り返しやスクロールを設定
- タッチ操作に配慮したボタンサイズを確保する
たとえば以下のように書くと、画面が小さいときに文字を小さくできます。
@media screen and (max-width: 600px) {
.accordion-title {
font-size: 14px;
}
}
このように、どの端末でも見やすくなる工夫をすることで、ユーザーにとって使いやすいアコーディオンになります。
アニメーションを追加する方法
アコーディオンにアニメーションを加えると、自然な開閉の動きが生まれて、見た目がよくなります。
ただパッと開くだけではなく、ふんわり広がるような動きにすることで、ユーザーにとって気持ちのよい操作感になります。
以下のような方法でアニメーションを追加できます。
- CSSのtransitionプロパティを使う
- heightやmax-heightを使って動きを出す
- opacityでフェード効果をつける
- transformでスライド感を出す
- JavaScriptで動きの制御を細かく調整
CSSの例は次のようになります。
.content {
max-height: 0;
overflow: hidden;
transition: max-height 0.3s ease;
}
input:checked + label + .content {
max-height: 300px;
}
このようにアニメーションを入れるだけで、ぐっと見栄えの良いアコーディオンになります。
動きがあると、情報の切り替えもわかりやすくなるのでおすすめです。
色やフォントのカスタマイズ方法
アコーディオンのデザインを自分のサイトに合わせて色やフォントを自由に変えることも大事です。
デザインが統一されていると、ユーザーが違和感なくページを読むことができます。
カスタマイズのポイントは以下の通りです。
- 見出し部分の背景色をブランドカラーにする
- 本文の文字色は黒やグレーなど読みやすい色にする
- フォントはサイト全体と統一する
- ホバー時の色変化で操作性をアップ
- 開いている時に色を変えて状態がわかるようにする
たとえば、見出しの背景色を変えるCSSはこう書きます。
.accordion-title {
background-color: #f0f0f0;
color: #333;
font-family: 'Arial', sans-serif;
}
こうした工夫をすることで、自分だけのオリジナルなアコーディオンが簡単に作れます。
デザインのベストプラクティス
アコーディオンのデザインには、押さえておくと役立つコツがいくつかあります。
とくにユーザーが初めてそのページを見るときでも、迷わずに使えるようにすることが大切です。
以下のようなベストプラクティスを覚えておきましょう。
- クリックできる場所は見た目でわかるようにする
- 開いた状態と閉じた状態がすぐにわかるデザインにする
- コンテンツの区切りがハッキリするように余白を取る
- 読み込み中にちらつかないように初期表示を調整
- 説明文やアイコンで操作方法を示す
これらを意識するだけで、使いやすさがグッと上がるアコーディオンになります。
特に初心者の方でも取り入れやすい工夫ばかりなので、ぜひ実践してみてください。
ユーザー体験を意識した工夫
最後に、アコーディオンの使い心地をよくするためにユーザー体験(UX)を考えた工夫が大切です。
見た目だけでなく、誰でも使いやすいと感じる作りにすることで、ページ全体の満足度が上がります。
特に意識したいポイントは次の通りです。
- アコーディオンの中身を短くまとめて読みやすくする
- 重要な情報を上に、補足は下に置く
- スマホ操作でもボタンが押しやすい大きさにする
- アニメーションは速すぎず遅すぎず自然な速度にする
- 初めて見る人でも直感的に使えるようなデザインにする
こういった工夫を加えることで、ユーザーが気持ちよく使えるアコーディオンになります。
誰かがサイトを見て「使いやすい!」と思ってくれるような設計を目指しましょう。
実用的なアコーディオンの応用パターン
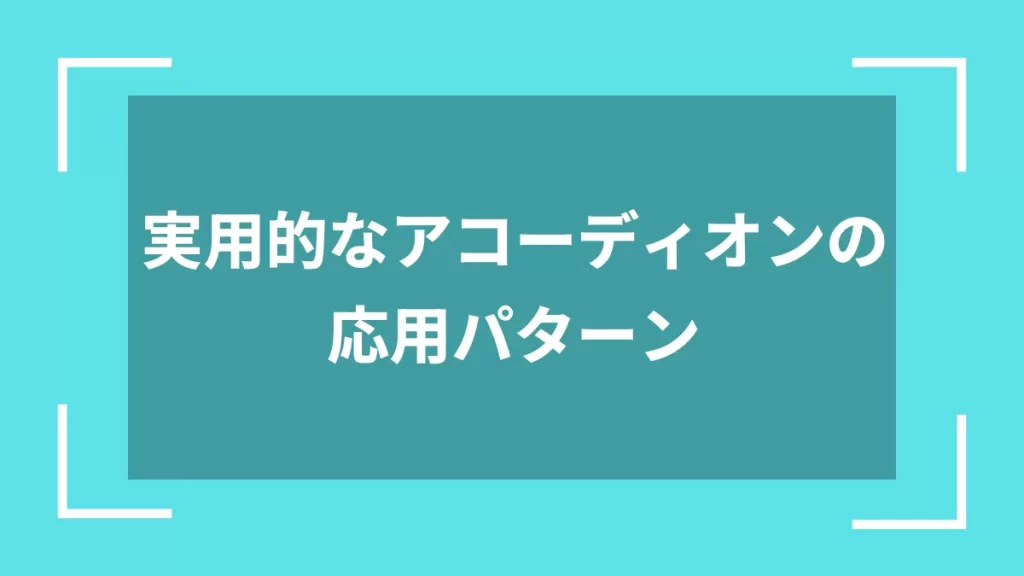
FAQセクションへの応用
アコーディオンの最も代表的な使い方のひとつが、FAQ(よくある質問)に使う方法です。
よくある質問の中から自分に関係のあるものだけを開いて見られるので、ユーザーにとってとても便利です。
また、たくさんの質問をひとつのページにまとめても、スッキリ見やすくなります。
FAQに使うときのポイントは以下の通りです。
- 質問は目立つように太字で書く
- 答えの部分は短く簡単に書く
- 開いたときの背景色を変えると見やすい
- すべて閉じた状態で読み込みすると見た目がきれい
- カテゴリごとにまとめると探しやすくなる
このようにFAQとアコーディオンはとても相性がよく、多くのウェブサイトで使われている人気の使い方です。
メニューやナビゲーションでの使用例
アコーディオンはメニューやナビゲーションでも便利に使えます。
たとえば、カテゴリがたくさんあるショッピングサイトや情報サイトでは、メニューを階層ごとに折りたたんで表示することで、画面をすっきり整理できます。
メニューでアコーディオンを使うときは、次のような工夫が必要です。
- 親メニューをクリックすると子メニューが表示される
- 選択されたメニューがひと目でわかるように色を変える
- スマホではタップしやすい大きさにする
- スクロールしなくても必要な情報が見えるように工夫する
- 開いている項目を記憶させたいときはJavaScriptを使う
このような工夫をすることで、使いやすくて迷わないナビゲーションが作れます。
特にスマートフォン対応のサイトでは効果的です。
フォーム内での使い方
入力項目が多いフォームにアコーディオンを使うと、使いやすくて親切なフォームになります。
たとえば、「基本情報」「配送情報」「支払い方法」などを分けて、必要なところだけ開くようにすることで、ユーザーの負担を減らせます。
フォームで使うときの注意点は以下の通りです。
- 入力中の内容が隠れないように自動で開いたままにする
- 入力エラーがあるときはアコーディオンを自動で開く
- それぞれの項目が何のためにあるか説明を加える
- 全体の流れがわかるようにステップ表示も検討する
- モバイル対応をしっかりしておく
このようにアコーディオンを使えば、ユーザーが安心して情報を入力できるフォームが実現できます。
入力ミスを防ぐためにも有効です。
テーブルやリストとの組み合わせ
アコーディオンはテーブル(表)やリストと組み合わせることで、情報量が多いデータを見やすく整理することができます。
たとえば、注文履歴の詳細や社員名簿のプロフィールなど、必要なときだけ開くことで、画面を広く使えます。
以下は、テーブルと組み合わせるときのポイントです。
- 行の下に詳細データを折りたたんで表示する
- 開いた部分のデザインは背景色などで区切る
- 開閉にアニメーションをつけてスムーズにする
- モバイル表示では縦型レイアウトに切り替える
- 読み込み速度を考えて最初は閉じた状態にする
この方法は、見た目も整って情報もわかりやすいので、業務系のウェブアプリや管理画面にもよく使われています。
スライドやタブとの併用方法
アコーディオンは、スライドやタブと組み合わせて使うことで、さらに高度なUI(ユーザーインターフェース)を作ることができます。
たとえば、タブでカテゴリを切り替えながら、その中にアコーディオンで詳細を入れる、というような構成です。
組み合わせるときの工夫は以下の通りです。
- タブとアコーディオンの役割を明確に分ける
- 動きが多すぎないようにアニメーションのバランスを取る
- ユーザーが今どこにいるのか迷わないようにデザインする
- JavaScriptで動きを整理し、競合しないようにする
- アクセシビリティ(使いやすさ)も考える
このような工夫をすると、多機能でも混乱しないインターフェースになります。
特に情報量が多いページにおすすめです。
SEOに配慮した構造の工夫
アコーディオンを使うと情報が隠れるので、SEO(検索エンジン対策)とのバランスも考える必要があります。
検索エンジンが内容を正しく読み取れるように、HTML構造をしっかり作ることが大切です。
SEOに強いアコーディオンのポイントは以下の通りです。
- コンテンツは最初からHTMLに書いておく
- JavaScriptで後から追加するのではなく、CSSで隠す
- 見出しタグ(h2やh3など)を正しく使う
- 開閉の状態にかかわらず、内容が読み込まれているようにする
- モバイルファーストで設計する
このように作れば、アコーディオンを使っても検索結果にちゃんと反映されるので安心です。
見やすさとSEOの両立を目指しましょう。
アクセシビリティ対応のポイント
アコーディオンは見た目だけでなく、誰にでも使えるようにすること(アクセシビリティ)も大切です。
キーボードだけで操作できることや、読み上げソフトでも正しく読めることがポイントです。
以下のような配慮を加えることで、アクセシビリティが高くなります。
- ARIA属性(aria-expandedなど)を設定する
- ラベルやボタンに役割(role)を明示する
- キーボード操作(TabキーやEnterキー)に対応する
- 画面リーダーで読まれるテキストを用意する
- 視覚的な強調だけでなく、構造的に情報を伝える
こうした工夫をすることで、すべての人が快適に使えるアコーディオンになります。
誰でも同じように使えることは、今のウェブではとても大事です。
HTMLアコーディオンの実装でよくある質問と対処法
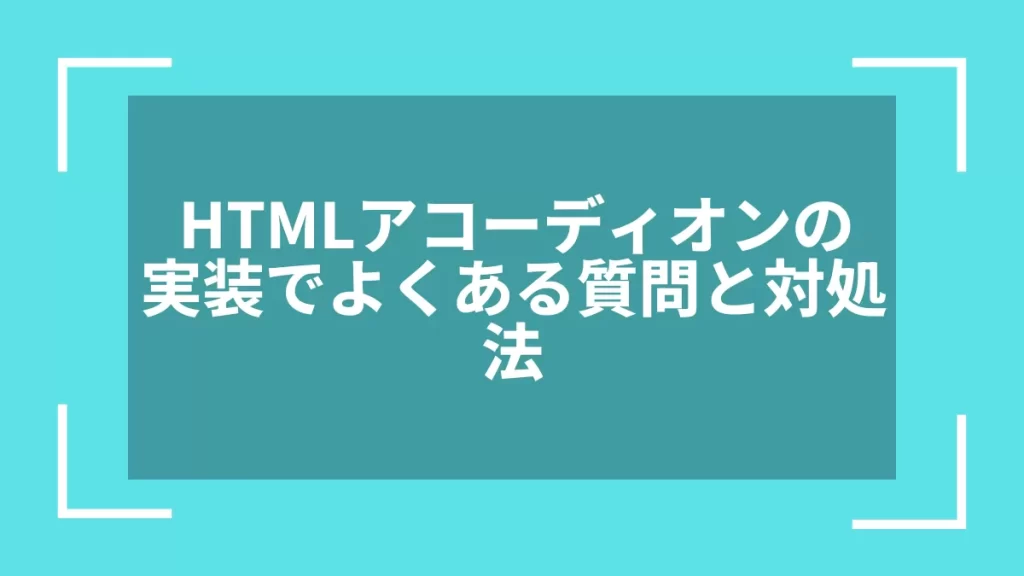
動作しないときの原因と対策
HTMLアコーディオンを作ったけれど、なぜか動かないということはよくあります。
そんなときは、よくある間違いをチェックしてみることが大切です。
とても簡単なミスが原因になっていることも多いです。
以下に、よくある原因とその対策をまとめました。
- IDとlabelのfor属性が一致していない
- CSSのセレクタが間違っている
- JavaScriptが読み込まれていない
- HTMLタグの閉じ忘れがある
- displayやvisibilityの指定が正しくない
これらをひとつひとつ確認していけば、ほとんどのエラーはすぐに解決できます。
焦らず、落ち着いて見直すことがポイントです。
スマホで正しく動かない場合の対応
パソコンでは問題なくても、スマホではうまく動かないことがあります。
スマホは画面が小さく、指で操作するため、特別な注意が必要です。
スマホで問題が出やすい点とその対策を紹介します。
- タップ範囲が小さすぎて操作しにくい → ボタンのサイズを広げる
- 文字が小さくて読めない → メディアクエリでフォントサイズを調整
- アニメーションが重くてカクカクする → 軽量なCSSアニメーションを使う
- 開いた内容が画面からはみ出る → 幅を100%に設定する
- 画面回転で表示が崩れる → レスポンシブデザインを意識する
こういった対策をすることで、スマホでも快適にアコーディオンを使えるようになります。
今の時代はスマホからの閲覧が多いので、とても大事なポイントです。
アニメーションが滑らかでないときの改善策
アコーディオンを開閉するときに、動きがガクガクして見づらいと感じることがあります。
それはアニメーションの設定やスタイルの組み方が関係している場合が多いです。
以下のポイントを見直すことで、なめらかな動きになります。
- transitionのプロパティを適切に使う
- max-heightを使い、heightは避ける
- transformやopacityを組み合わせる
- JavaScriptを使うならrequestAnimationFrameを活用
- CSSアニメーションの時間は0.3秒前後が目安
たとえば、CSSで次のように書くとスムーズな動きになります。
.content {
max-height: 0;
overflow: hidden;
transition: max-height 0.4s ease;
}
input:checked + label + .content {
max-height: 300px;
}
このように調整することで、ストレスなく見やすいアコーディオンになります。
複数アコーディオンの連動処理
複数のアコーディオンを使っているときに、ひとつを開いたら他を自動で閉じたいという場面があります。
これにはJavaScriptを使って、開閉の動きをコントロールする必要があります。
この処理を行うときのステップは以下の通りです。
- すべてのアコーディオン要素を取得する
- クリックされた要素以外のコンテンツを閉じる
- 現在の要素を開く処理を実行する
- イベントリスナーでクリック時に切り替え
- アニメーションを加えるとより自然な動きに
以下はシンプルなJavaScriptのコード例です。
const titles = document.querySelectorAll('.accordion-title');
titles.forEach(title => {
title.addEventListener('click', () => {
titles.forEach(t => {
if (t !== title) t.classList.remove('active');
t.nextElementSibling.style.display = 'none';
});
title.classList.toggle('active');
const content = title.nextElementSibling;
content.style.display = content.style.display === 'block' ? 'none' : 'block';
});
});
このように設定することで、すっきりとした動きで切り替えができるアコーディオンになります。
初期状態で開いておく設定方法
あるアコーディオンだけを最初から開いた状態にしておきたいときには、HTMLやCSSで初期設定をしておく必要があります。
とくにFAQなどでよくある質問を先に見せたい場合に便利です。
以下の手順で設定します。
- チェックボックスにchecked属性をつける
- CSSで:checkedのスタイルを反映させる
- JavaScriptを使う場合はDOMContentLoadedで初期設定
- 見た目のデザインも「開いている」状態に合わせる
- アニメーションのタイミングに注意する
HTMLでの設定例は以下の通りです。
<input type="checkbox" id="faq1" checked>
<label for="faq1">質問1</label>
<div class="content">答えの内容がここに入ります</div>
このように初期表示を工夫することで、見せたい情報を最初にユーザーに届けることができます。
読み込み時のちらつきを防ぐ方法
ページを開いたときにアコーディオンの中身が一瞬だけ見えてしまう、いわゆる「ちらつき」が起こることがあります。
これはCSSの読み込みやJavaScriptの処理タイミングが原因で起こります。
この問題を防ぐには以下の方法が有効です。
- CSSで初期状態を明示的に非表示にする
- JavaScriptが読み込まれる前に状態が変わらないようにする
- bodyに「読み込み完了後に表示」クラスを追加する
- アニメーションは表示後にだけ発動するように設定
- 画面外のアコーディオンは遅延表示も検討する
たとえば、次のようなCSSでちらつきを防げます。
body:not(.loaded) .content {
display: none;
}
window.addEventListener('load', () => {
document.body.classList.add('loaded');
});
このように読み込み時の視覚的なトラブルを防ぐ工夫をすると、より品質の高いサイトになります。
軽量化とパフォーマンス向上の工夫
アコーディオンの数が増えてくると、表示が遅くなったり動作が重くなったりすることがあります。
そうならないために、できるだけ軽くて速い実装を心がける必要があります。
以下のような方法でパフォーマンスを改善できます。
- JavaScriptは必要な部分だけで処理する
- CSSアニメーションを中心に構成する
- DOMの操作回数を減らす
- 遅延読み込みや非同期処理を取り入れる
- 画像やアイコンの読み込みサイズを抑える
このようにパフォーマンスを意識して作ることで、ユーザーにとって快適な操作感を保つことができます。
特にスマートフォンでは重要なポイントです。
まとめ
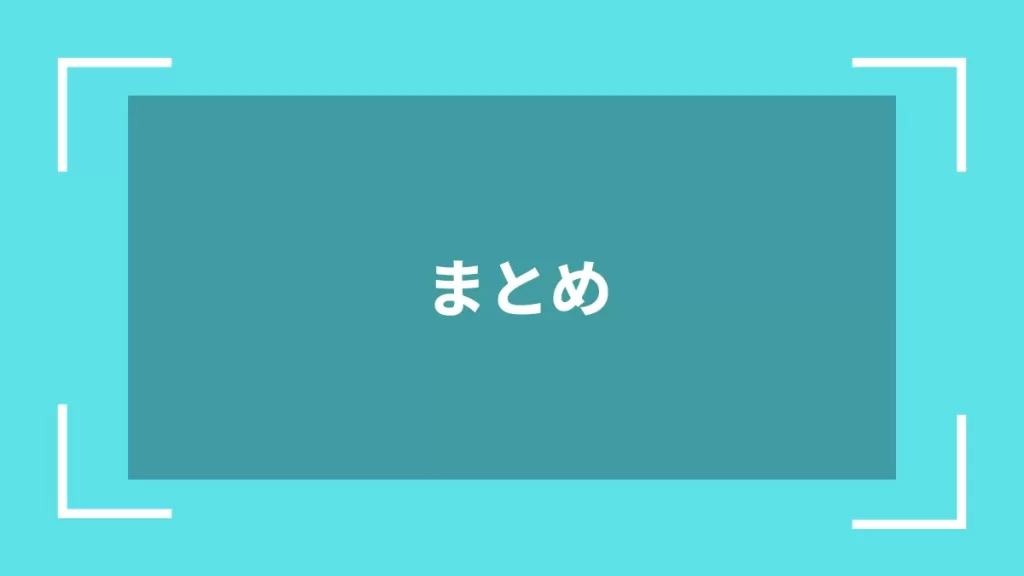
これまで紹介してきた内容をふり返って、特に大事なポイントを簡単にまとめます。
- HTMLとCSSだけでもアコーディオンは作れる
- JavaScriptを使えば動きや連動がもっと自由になる
- シンプルで見やすいデザインがユーザーにやさしい
- フォームやメニュー、FAQなどいろいろな場所で使える
- スマホ対応やアクセシビリティにも気をつける
まずは簡単なアコーディオンをひとつ作ってみて、少しずつ自分のサイトに合わせて応用していきましょう!

















