HTMLでボタンを作ったけど、「クリックしてもページが移動しない」ってことありますよね。
見た目はボタンなのに、思ったようにリンクとして動いてくれないと困ってしまいます。
今回は、HTMLでボタンを使ってリンクを実現する正しい方法について、わかりやすく解説します。
aタグとbuttonタグの違いや、それぞれの使い方、よくあるミスの対処法までしっかり説明します。
この内容を知っておけば、誰でも「正しく動くリンク付きボタン」が作れるようになりますので、ぜひ最後まで読んで参考にしてください。
HTML初心者の方でも安心して読み進められる内容になっています。
HTMLでボタンにリンクを設定する基本的な方法
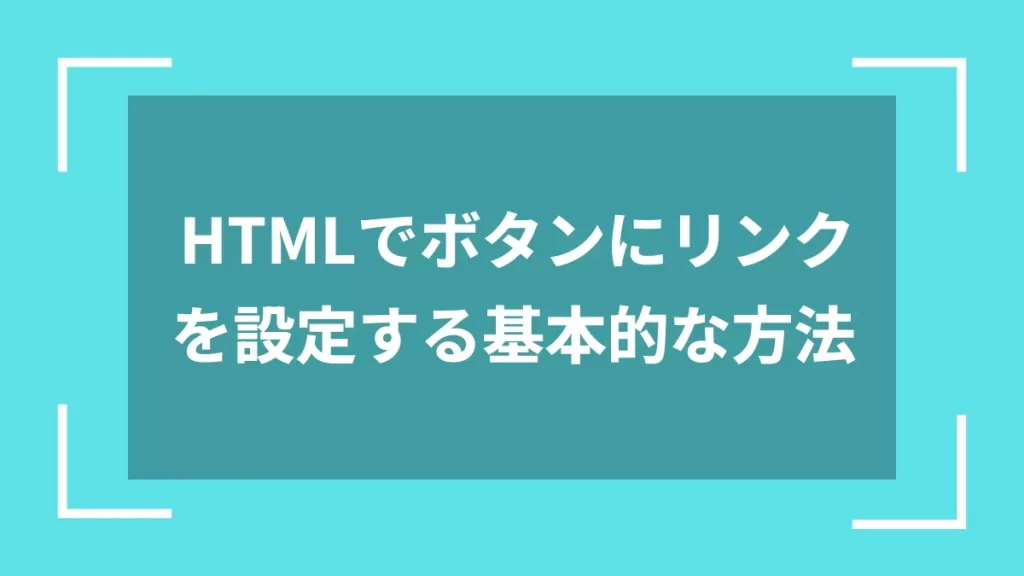
buttonタグとaタグの違い
HTMLで「リンク付きボタン」を作るとき、よく使われるのが「buttonタグ」と「aタグ」です。
この2つにははっきりとした役割の違いがあります。
それを知って使い分けることが、正しいHTMLを書くうえでとても大事です。
まず「aタグ」は本来「リンク」を作るためのタグです。
ユーザーを別のページや場所へ移動させる目的があります。
一方で「buttonタグ」は、「フォームの送信」や「JavaScriptによる動作実行」に使われます。
以下に、両者の主な違いをまとめます。
- aタグはページ遷移に使う
- buttonタグはページ内操作やイベント実行に使う
- SEOやアクセシビリティの観点ではaタグが推奨される
- buttonタグはformと一緒に使うとフォーム送信ボタンになる
- CSSで見た目はどちらもボタンのようにできる
このように、目的に合ったタグを選ぶことで、検索エンジンにもやさしく、ユーザーにもわかりやすいサイトが作れます。
aタグを使ってボタン風に見せる方法
リンクをボタンのように見せたいときは、aタグを使ってCSSで見た目を整えるのが一般的です。
この方法なら、正しいリンクの構造を保ちながら、視覚的にもボタンに見せることができます。
まずはaタグでリンクを作ります。
次にCSSを使って、背景色や枠、文字のスタイルを変更します。
- display: inline-blockでボタンのようなサイズ調整をする
- paddingで上下左右に余白をつける
- background-colorで色をつける
- border-radiusで角を丸くする
- text-decoration: noneで下線を消す
このような設定をすることで、aタグでも見た目はしっかりとしたボタンになります。
ただし、見た目だけでなく「クリックするとどこかに移動する」という役割も正しく持っていることがポイントです。
buttonタグでJavaScriptを使って遷移する方法
buttonタグでリンクのように遷移させたいときは、JavaScriptを使ってページを移動させる方法があります。
この方法は、見た目も動作もボタンのようにしたいときに使われます。
実際のコードでは、buttonタグにonclick属性を使い、JavaScriptでlocation.hrefを変更します。
- onclick=”location.href=’URL'”という形式で書く
- イベント発火後にURL先へジャンプする
- JavaScriptが無効な環境では動作しない
- アクセシビリティ対応が難しくなる場合がある
- SEOに対する効果は期待できない
JavaScriptを使う方法は便利ですが、リンク先へただ移動させるだけならaタグを使ったほうが安全で確実です。
buttonタグ+JavaScriptは「特別な処理を伴うボタン」で使うようにしましょう。
form要素と組み合わせた遷移方法
フォームと一緒に使う場合、buttonタグはとても便利です。
formタグの中にbuttonを入れると、フォームの送信ボタンとして動作します。
action属性を使えば、指定したURLへ遷移できます。
この方法は、入力フォームを送信したあとで他のページへ移動させるときに使います。
- formタグ内にbuttonタグを置く
- formのaction属性にリンク先のURLを設定する
- methodはGETかPOSTを使う
- サーバー側で処理を行うことが多い
- URLにパラメータを付けたいときに便利
ただし、ただのリンクだけならこの方法は適しません。
これはあくまでも「フォーム送信」として使う方法です。
HTML5で推奨される実装パターン
HTML5では、意味のあるマークアップを推奨しています。
リンクにはaタグ、ボタンにはbuttonタグと、タグの本来の意味を守って使うことが大切です。
これにより、SEOやアクセシビリティにも良い影響があります。
特に、リンクにJavaScriptを使ってボタン風にするのは避けるべきです。
なぜなら、スクリーンリーダーや検索エンジンが正しく内容を理解できなくなるからです。
以下のような実装が推奨されます。
- リンクにはaタグを使う
- フォーム送信にはbuttonタグを使う
- 見た目の装飾はCSSに任せる
- 意味のある構造を意識する
- JavaScriptは必要な場面だけにする
このように、HTML5のルールに沿ってコードを書くことで、後から見てもわかりやすく、トラブルも起きにくくなります。
リンクとして正しいマークアップの考え方
HTMLでは「この要素は何をするのか」という意味を持つことがとても大切です。
リンクとして正しく機能させたいなら、マークアップの時点でその意味をちゃんと表現する必要があります。
たとえば、見た目がボタンでも、クリックしてページが変わるなら、それはリンクです。
なのでaタグを使うのが正解です。
正しいマークアップをするために、以下のポイントを意識しましょう。
- ページ移動には必ずaタグを使う
- デザイン目的でタグを変えない
- aria-labelなどで補足情報を加える
- 同じ役割には同じタグを使う
- 構造をわかりやすくすることで保守性もアップ
これを守るだけで、HTMLがもっとわかりやすくなり、ユーザーにとっても親切なサイトになります。
タグの意味を意識して使い分けましょう。
HTMLボタンでリンクを作る際の注意点
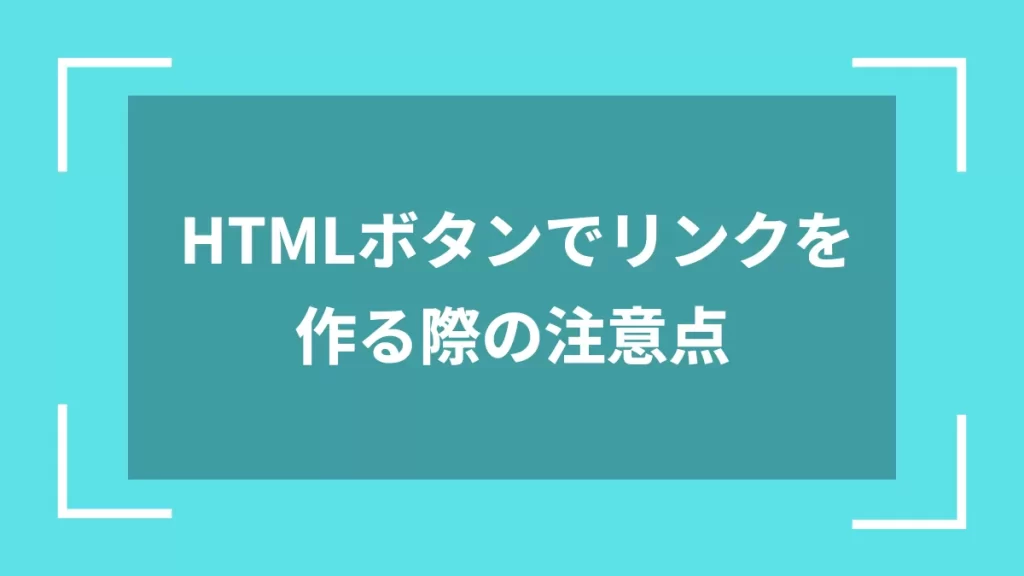
アクセシビリティの観点からの注意点
HTMLでボタンをリンクとして使う場合、アクセシビリティをしっかり意識することがとても大切です。
視覚に頼れないユーザーや、キーボードで操作する人たちにとっては、見た目だけではなく「正しい意味を持ったタグ」が重要になります。
アクセシビリティを考えたときの注意点は次のとおりです。
- aタグはリンクとして読み上げられる
- buttonタグはボタンとして読み上げられる
- onclickで遷移するbuttonはリンクと認識されにくい
- キーボード操作で移動できるようにする
- スクリーンリーダーに正しく伝わるようにaria属性を使う
これらを守れば、どんな人にも使いやすいウェブページになります。
見た目よりも「意味」を大切にしましょう。
SEOへの影響と正しい実装
ボタンをリンクのように使った場合、SEOにも影響が出ることがあります。
検索エンジンは、ページの構造を見て、どの部分がリンクなのかを判断しています。
正しくaタグを使うことで、クローラーがリンクとして理解し、評価の対象になります。
以下はSEOの面から見た注意ポイントです。
- aタグで書かれたリンクだけがクローラーに認識される
- JavaScriptだけで遷移するリンクはSEOで不利になる
- リンク先に重要なページがある場合はaタグを使う
- rel属性やtitle属性で意味を補足するのも有効
- 意味のあるテキスト(アンカーテキスト)を使う
SEOを意識するなら、ボタンではなく正しいaタグを使って実装することが成功のカギです。
外部リンクと内部リンクでの違い
HTMLでボタンリンクを作るとき、リンク先が「外部サイト」なのか「自分のサイト内」なのかによって使い方が変わります。
特に外部リンクを使うときは、ユーザーの使いやすさと安全性にも配慮しなければいけません。
まずは、外部リンクと内部リンクの違いを理解しましょう。
- 内部リンク:自分のサイト内のページへ移動
- 外部リンク:別のドメインやサイトへ移動
- 外部リンクではtarget=”_blank”で新しいタブを使う
- rel=”noopener noreferrer”を付けてセキュリティ対策
- 内部リンクはサイト構造を考えて設置する
どちらのリンクもaタグを使うのが基本です。
リンク先の種類によって、使い方を工夫することが大切です。
JavaScriptに依存する場合のリスク
HTMLでボタンリンクをJavaScriptに頼って動かすと、いくつかのリスクが発生します。
特に、JavaScriptがオフになっている環境や、読み込みエラーが起きた場合には、ボタンが全く機能しないことがあります。
ここではJavaScript依存による主な問題点を紹介します。
- JavaScriptが動かないとリンクが機能しない
- 読み込みタイミングによって処理がずれる可能性がある
- クローラーがリンクとして認識できないことがある
- アクセシビリティが下がる原因になる
- 保守性が悪くなることも多い
これらの理由から、可能な限りリンクはaタグで書き、JavaScriptは補助的に使うようにするのが良いです。
タブ移動やスクリーンリーダー対応
タブキーで移動したり、スクリーンリーダーを使ってページを読んだりする人にとって、HTMLの正しい使い方はとても重要です。
タグの使い方を間違えると、ユーザーが操作できなくなることもあります。
たとえば、見た目がボタンでもaタグであればタブ移動が可能です。
buttonタグもタブ移動できますが、JavaScriptで無理に動かすと移動できないこともあります。
スクリーンリーダー対応で意識すべき点は以下の通りです。
- aタグにはリンク先の内容がわかるテキストを入れる
- aria-labelで役割や内容を補足する
- キーボードだけで操作できるようにする
- role属性を乱用しない
- 読み上げ順が自然になるように構造を整える
アクセシビリティを意識したHTMLを書くことで、誰にとってもやさしいウェブページになります。
HTMLとCSSの役割分担を意識する
HTMLとCSSは、それぞれ役割が違います。
HTMLは「構造」を、CSSは「見た目」を担当します。
ボタンリンクを作るときにも、この分け方を意識することで、コードがわかりやすくなり、管理しやすくなります。
たとえば、リンクをボタン風に見せたいときでも、構造としてはaタグを使い、見た目だけをCSSでボタンにします。
これは正しい使い方です。
役割分担を意識するためのポイントは次のとおりです。
- HTMLは意味と構造を表現する
- CSSは見た目やスタイルを整える
- 見た目だけのためにHTMLタグを変えない
- JSでできることでも、HTMLとCSSで対応できるならそちらを使う
- 保守性と再利用性が高まる
これを意識して実装するだけで、プロっぽいHTMLが作れるようになります。
タッチデバイスでのクリック判定
スマートフォンやタブレットなど、指で操作するタッチデバイスでは、クリック判定が少し違います。
そのため、ボタンやリンクの作り方によっては、タッチしても反応しにくくなることがあります。
特に重要なのは、タッチしやすい大きさと、はっきりした表示です。
タッチデバイス対応のポイントをまとめます。
- ボタンやリンクのサイズは最低でも48px四方
- 余白(padding)をしっかりとる
- 指でタップしても間違えにくいように配置する
- タップ時の視覚的なフィードバックを用意する
- hoverだけでなく:activeのスタイルも設定する
タッチ操作を考えた作り方をすれば、スマホユーザーにとっても快適な体験を提供できます。
CSSでリンク付きボタンをデザインするテクニック
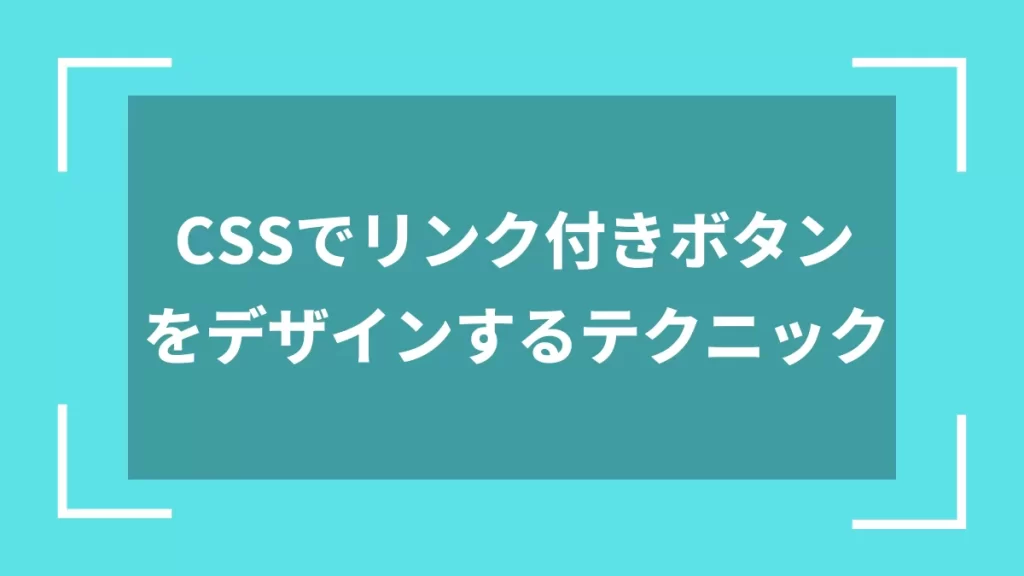
aタグをボタン風にする基本スタイル
HTMLのaタグを使って、リンクにボタンのような見た目をつけるのはとてもよく使われるテクニックです。
タグの意味を保ちながら、見た目を整えるにはCSSでしっかりスタイリングすることが大切です。
以下のような基本スタイルを押さえることで、誰でも簡単に「リンク付きボタン」を作れます。
まずは以下のようなポイントを意識しましょう。
- display: inline-blockで幅と高さを自由に設定できるようにする
- paddingでボタンらしい余白をつける
- background-colorでボタンの色を設定する
- border-radiusで角を丸くする
- text-decoration: noneでリンクの下線を消す
これらを設定すれば、aタグでもしっかりボタンに見えるようになります。
タグの意味を守りながら、見た目を調整できるのがこの方法の良いところです。
hover・active時の視覚効果の付け方
リンク付きボタンを作るとき、マウスを乗せたとき(hover)やクリックしたとき(active)の効果をつけると、ユーザーにとってわかりやすくなります。
これらの効果は「視覚的なフィードバック」としてとても重要です。
次のような設定で、hoverやactiveの効果を付けられます。
- hoverで背景色を少し暗くする
- hoverで影(box-shadow)を追加する
- activeでボタンを少し凹ませる
- transitionを使ってなめらかに動かす
- 色の変化だけでなくカーソルの形(pointer)も忘れずに
これらを使うことで、ボタンが「ちゃんと反応している」とユーザーに伝えることができます。
小さなことですが、信頼感につながります。
レスポンシブ対応ボタンの作り方
スマートフォンやタブレットなど、さまざまな画面サイズに対応するためには「レスポンシブ対応」が欠かせません。
リンク付きボタンも、デバイスに応じてサイズや配置が変わるようにしておくと、どこでも使いやすいページになります。
レスポンシブ対応のボタンを作るときは、以下のポイントを意識しましょう。
- 幅を%で指定する
- 文字サイズはemやremを使う
- メディアクエリ(@media)で画面サイズごとに調整する
- flexboxやgridで配置を整える
- タップ領域が小さくならないようpaddingを広めにとる
どんなデバイスでもボタンがしっかり表示されるように作れば、ユーザーの満足度も大きく上がります。
アイコン付きリンクボタンの作成
リンク付きボタンにアイコンを入れると、見た目がわかりやすくなり、操作もしやすくなります。
たとえば「右矢印」や「虫眼鏡」のようなアイコンは、何をするボタンなのかを一目で伝える力があります。
アイコン付きボタンを作るには、文字と一緒に画像やSVG、Webフォントのアイコンを並べます。
- Font AwesomeやMaterial Iconsを使う
- アイコンとテキストの間に余白を入れる
- アイコンだけの場合はaria-labelで説明をつける
- アイコンの色や大きさもボタンに合わせて調整する
- インラインSVGならカスタマイズがしやすい
視覚的にも楽しくなるので、リンクボタンにアイコンを加えるのはおすすめの方法です。
ボタンサイズとクリック領域の最適化
ボタンをデザインするときに忘れてはいけないのが「クリックしやすいサイズ」です。
見た目がキレイでも、指でタップしにくいボタンは使いにくく感じられてしまいます。
特にスマホではクリック領域の最適化が重要です。
次のポイントを押さえれば、操作しやすいボタンになります。
- 最小でも横48px×縦48pxを目安にする
- 周囲の要素と十分な間隔を空ける
- 余白(padding)を広くとることで押しやすくなる
- 誤タップを防ぐために連続で配置しすぎない
- タッチ用に:activeの状態も意識する
見た目と使いやすさのバランスを考えて、クリックしやすいボタンを作るようにしましょう。
カスタムプロパティを使った管理法
CSSのカスタムプロパティ(変数)を使えば、ボタンの色やサイズを一か所で管理できるようになります。
これにより、複数のボタンがある場合でも、後からまとめて変更しやすくなります。
カスタムプロパティを使う方法は以下のとおりです。
- –main-colorや–btn-radiusのように変数名を決める
- :rootセレクタで全体に定義する
- ボタンのスタイル内でvar()を使って呼び出す
- テーマ変更にも柔軟に対応できる
- 保守性・再利用性が高くなる
CSSの管理がしやすくなるので、カスタムプロパティは今のWeb制作ではとても便利な機能です。
デザインとユーザビリティのバランス
リンク付きボタンは、見た目がオシャレでも、使いにくいと意味がありません。
かっこいいだけでなく、ユーザーがすぐにわかってすぐに使えるようにすることが大切です。
デザインと使いやすさ、どちらも大事にするのがプロの仕事です。
バランスをとるために意識すべきことをまとめます。
- 色や形だけでなく役割が伝わること
- 押したときにすぐ反応するようにする
- 説明が必要なボタンはラベルをつける
- 機能ごとにデザインを少し変えて区別する
- ユーザーがどこを押せばいいか迷わないようにする
誰が見ても「わかりやすい」「使いやすい」と思えるボタンを目指しましょう。
見た目と機能、両方がそろってはじめて「いいデザイン」と言えます。
HTMLボタンリンクの実装に関するよくある質問とトラブル対処
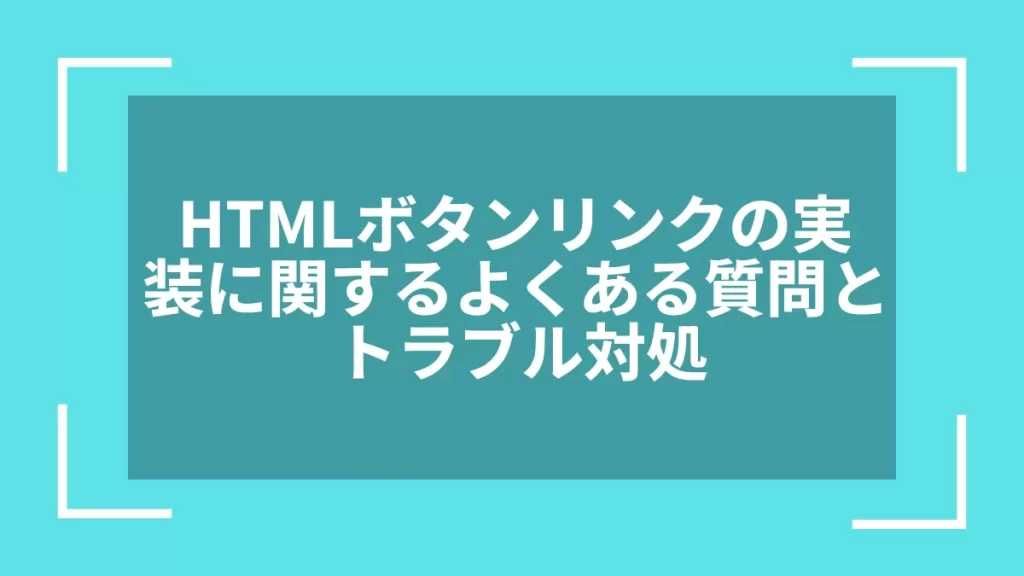
クリックしてもリンクが機能しない原因
HTMLでボタンを使ってリンクを設定したのに、クリックしてもページが移動しないというトラブルはよくあります。
この問題にはいくつかの原因が考えられるため、ひとつずつ確認していくことが大切です。
以下に、よくある原因をまとめました。
- JavaScriptのエラーが発生している
- onclick属性の記述ミス
- aタグのhref属性が空白または「#」だけになっている
- buttonタグにtype=”submit”が付いていてformが絡んでいる
- CSSやJavaScriptでイベントが上書きされている
リンクが動かないときは、上記のようなポイントを順に確認してみてください。
コードの見直しで改善できることがほとんどです。
CSSで装飾が反映されない場合の対処
HTMLでボタンリンクを作ってCSSでデザインしたはずなのに、なぜかスタイルが反映されないことがあります。
これは初心者がよくぶつかる問題で、原因を知っておけばすぐに解決できます。
スタイルが効かない原因には以下のようなものがあります。
- セレクタの指定ミス
- クラス名やID名の間違い
- CSSファイルが正しく読み込まれていない
- ブラウザキャッシュが残っていて反映されない
- 同じスタイルが別の場所で上書きされている
こうした点を見直すことで、装飾が正しく反映されるようになります。
まずはセレクタとCSSの読み込み状況を確認しましょう。
遷移先が新しいタブで開かないときの対処法
リンクを新しいタブで開かせたいのに、同じウィンドウで開いてしまうことがあります。
このようなときは、HTMLの属性が正しく使われているかどうかを確認しましょう。
新しいタブで開くためには、以下の設定が必要です。
- target=”_blank”をaタグに追加する
- rel=”noopener noreferrer”も同時に付ける
- JavaScriptを使っている場合はwindow.openを使う
- 一部のブラウザやポップアップブロック設定により開かないこともある
- ユーザーの操作に依存する場面では自動遷移が制限される
こうした設定を正しく行えば、新しいタブでスムーズに開くようになります。
特にtargetとrel属性はセットで使うのがセキュリティ的にも安心です。
スマホでボタンが反応しない原因
パソコンでは正常に動作するのに、スマホでタップしてもボタンが反応しない場合は、タッチ操作特有の原因が考えられます。
画面サイズやタッチ領域を意識しない作り方をしていると、こうした不具合が起きやすくなります。
主な原因を以下にまとめます。
- タッチ領域が小さすぎる
- ボタンが他の要素に重なっている
- JavaScriptイベントがスマホ用に対応していない
- positionやz-indexの設定ミス
- hover効果しか用意されていない
スマホ対応には「指での操作」を前提に、見た目と機能の両方を考えることが必要です。
余白を広くとり、簡単にタップできるようにすることで、操作性が大きく向上します。
JavaScriptエラーによる動作不良の確認方法
HTMLボタンリンクが動かないとき、JavaScriptのエラーが原因である場合が多いです。
特にonclickイベントやDOM操作にバグがあると、リンク自体が機能しなくなることがあります。
エラーの確認には以下の方法が役立ちます。
- ブラウザの開発者ツール(F12)を使う
- Consoleタブでエラー内容をチェックする
- 関数名や変数名のスペルミスを見直す
- イベントリスナーが正しく設定されているか確認する
- 外部スクリプトの読み込み失敗がないかチェックする
エラーを一つずつ潰していくことで、ボタンリンクが正しく動作するようになります。
JavaScriptを使う場合は、デバッグの習慣をつけましょう。
HTMLバリデーションエラーの対処法
HTMLコードに間違いがあると、ボタンリンクがうまく動かなかったり、予期せぬレイアウト崩れを起こしたりします。
そんなときは「バリデーション」を使って、HTMLの文法エラーをチェックするのが効果的です。
対処法は以下のとおりです。
- W3Cのバリデーターでチェックする
- タグの閉じ忘れや入れ子構造の間違いを見つける
- 不要な属性や古い記述がないか確認する
- buttonタグやaタグに不正な属性を使っていないか見直す
- DOCTYPEやmetaタグも見直して整える
バリデーションエラーを放置すると、将来的に別の不具合が出る可能性があります。
エラーはできるだけ早く修正して、正しいHTMLを書くように心がけましょう。
ブラウザ間で見た目が異なるときの調整
同じHTMLとCSSを使っていても、ブラウザによってボタンリンクの表示が違うことがあります。
特に初期スタイル(User Agent Stylesheet)の違いによって、予想外の見た目になることがあります。
ブラウザ間の違いを減らすには、以下の対策が有効です。
- リセットCSSやNormalize.cssを使う
- paddingやmarginを明示的に指定する
- フォントやline-heightも同じに設定する
- borderやoutlineを確認しておく
- 動作確認は主要ブラウザで必ず行う
見た目が揃っていると、サイト全体がしっかりして見えます。
細かい差異にも注意して、すべてのユーザーに同じような体験を提供できるようにしましょう。
まとめ
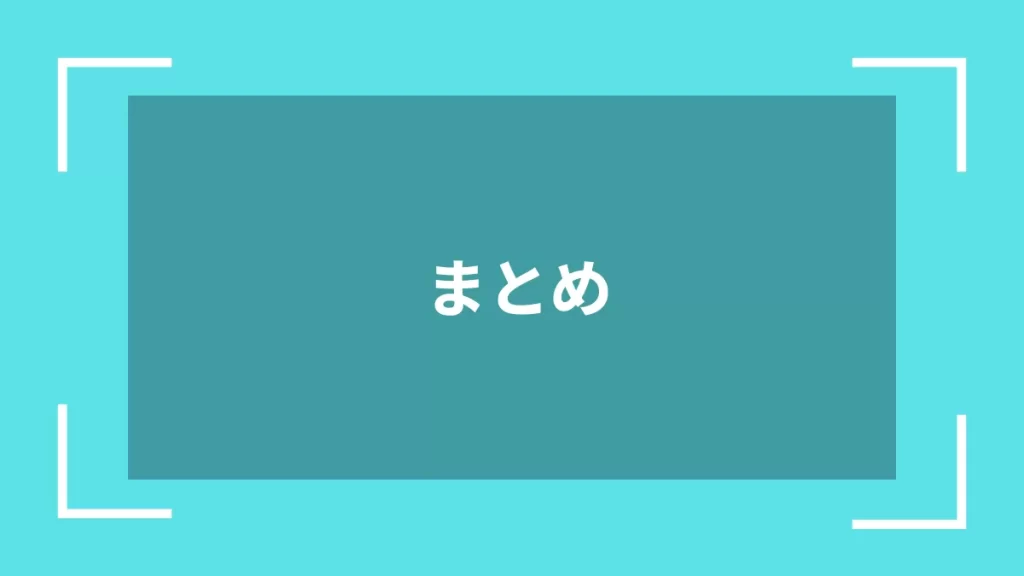
HTMLでボタンリンクを正しく使うには、タグの意味や使い方をしっかり理解しておくことが大切です。
今回紹介した内容の中でも、特に大事なポイントを以下にまとめます。
- リンクには基本的にaタグを使う
- ボタンの見た目はCSSで調整する
- JavaScript依存のリンクは避ける
- アクセシビリティとSEOに配慮する
- タッチやキーボード操作にも対応する
正しいタグを使って、誰でも使いやすいボタンリンクを作っていきましょう。
今日からあなたのHTMLも、もっとわかりやすくて親切なものになります。

















