画像に説明文をつけたいとき、どんなHTMLタグを使えばいいのか迷うことってありますよね。
文章の中に画像を入れるだけでは伝わらないことも多くて、うまく見せるのが難しいと感じたことがある方もいると思います。
そこで今回は、「figure HTMLタグ」についてくわしく説明します。
このタグは、画像や図にキャプション(説明)をつけたいときに使えるとても便利なタグです。
figureタグの使い方や、画像との正しい関係性を知ることで、検索エンジンにもわかりやすく、見る人にも伝わりやすいHTMLが作れるようになります。
Web初心者の方でも理解できるようにやさしく解説していきますので、ぜひ最後まで参考にしてみてください。
figureタグとは?HTMLにおける役割と基本的な使い方
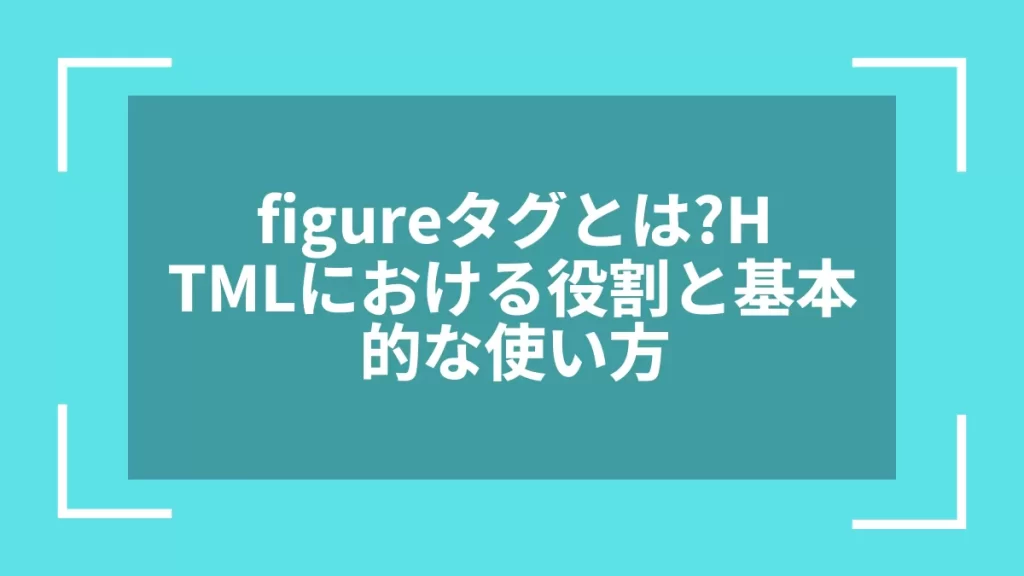
figureタグの定義と意味
figureタグは、HTML5から導入された意味を持つタグ(セマンティックタグ)のひとつで、主に図や写真、表、コードなどに使われます。
本文の流れとは少し独立した要素に対して、説明やキャプションを加えたいときに使われます。
特に、画像に対してキャプション(説明文)をつけたい場合に活躍します。
以下に、figureタグの基本的なポイントをまとめます。
- 画像や図を囲むためのタグ
- figcaptionタグとセットで使う
- コンテンツの文脈から独立した補足情報に使われる
- セマンティックに意味を持たせられる
- SEOにも有利になる可能性がある
このように、figureタグを使うことでHTMLの構造が分かりやすくなり、検索エンジンにも伝わりやすくなります。
HTMLにおけるfigureタグの正しい構文
figureタグの使い方はとてもシンプルですが、正しい構文を知っておくことが大切です。
ここでは基本の書き方を紹介します。
- <figure>タグで画像や図を囲む
- <img>タグで画像を表示する
- <figcaption>タグで説明文を加える
- figcaptionはfigure内に配置する
- 順番はimgの後でも先でもOK
このように、正しく構造を作ることで視覚的にも意味的にも分かりやすいマークアップになります。
figcaptionとの違いと使い方
figcaptionは、figureタグの中で使われる説明文用のタグです。
つまり、figureが「図の枠」だとしたら、figcaptionは「その図の説明」にあたります。
figcaptionの特徴を以下にまとめます。
- figureの中でのみ使える
- 画像や図の説明文を表示する
- 位置は前でも後でもよい
- HTMLの構造を明確にする
- アクセシビリティが向上する
このように、figcaptionを使うことでユーザーにも検索エンジンにも優しいHTMLが作れます。
画像以外にも使える?figureタグの応用例
figureタグは画像だけに使うものではありません。
他にも、図表、コードスニペット、地図などにも使うことができます。
つまり、本文とは独立した意味を持つ内容であれば使用可能です。
たとえば以下のようなケースでも使えます。
- グラフやチャートの説明をつける
- 引用したコードにタイトルをつける
- Googleマップなどの地図の解説を入れる
- 動画に字幕や注釈をつける
- 統計表などの補足情報を入れる
このように、画像以外にもfigureタグは幅広い場面で使えるとても便利なタグです。
他のHTMLタグとの組み合わせ方
figureタグは、他のタグと組み合わせることでさらに強力になります。
特に、imgやvideo、pre、tableなどと一緒に使うことが多いです。
以下に組み合わせの例を紹介します。
- <figure>+<img>:画像とキャプション
- <figure>+<video>:動画と説明文
- <figure>+<pre>:コードとその説明
- <figure>+<table>:表と注釈
- <figure>+SVGタグ:ベクター画像の図解
このように、figureタグは意味のあるマークアップを実現する重要な要素として、多くのタグと一緒に使われます。
figureタグを使うべきケースと使わない方がいいケース
figureタグは便利ですが、すべての場面で使えばいいというわけではありません。
使うべき場面と、避けた方がよい場面を理解しておくことが大切です。
使うべきケースは以下の通りです。
- 画像に説明文をつけたいとき
- 図表や動画を解説付きで見せたいとき
- コンテンツの補足情報を独立して見せたいとき
- SEOやアクセシビリティを強化したいとき
- 文章とは関係があるが、流れから独立した要素の場合
逆に、使わない方がいい場面は以下です。
- 飾りとしての画像
- 文章の流れに密接に関わる画像
- キャプションが不要な画像
- 意味的な補足がない素材画像
これらを意識することで、より意味のあるHTMLマークアップが実現でき、ユーザーにも検索エンジンにも伝わるページ作りができます。
画像とfigureタグの正しい関係性とは?

画像にキャプションを付ける理由
画像にキャプションを付ける理由は、見ている人に画像の意味や目的を伝えるためです。
画像だけでは「これは何を表しているのか?」がわからないことがあります。
そんなときに、キャプションがあるとすぐに理解できます。
視覚的な情報と文章の説明が合わさると、内容がより伝わりやすくなるのです。
具体的な理由は以下の通りです。
- 画像の意味が明確になる
- ユーザーの理解が早くなる
- アクセシビリティが向上する
- SEOにも効果がある
- 画像が独立した情報として成立する
このようにキャプションは、ただの飾りではなく情報としての価値を持たせる重要な要素になります。
figureタグとimgタグの組み合わせ
figureタグとimgタグは、セットで使うのが基本です。
この組み合わせによって、画像を意味のある情報としてマークアップすることができます。
imgタグ単体では画像を表示するだけですが、figureで囲むことで画像の役割がより明確になります。
ここでは、使い方の流れを整理します。
- <figure>タグで全体を囲む
- <img>タグで画像を表示
- <figcaption>タグで説明文を加える
- 構文が正しいとSEOにも効果的
- imgのalt属性も忘れずに設定
このように、figureとimgを組み合わせることで、画像の意味や文脈が明確になり、見やすく伝わりやすいコンテンツを作ることができます。
SEOに有効な画像構造の作り方
画像をSEOに活かすためには、HTMLの構造をしっかり整えることが大切です。
ただ表示するだけではなく、意味を持たせることで検索エンジンにも正しく伝えることができます。
以下に、SEOに強い画像構造を作るポイントをまとめます。
- figureタグで画像全体を囲う
- figcaptionで説明文をつける
- imgにalt属性で画像の内容を説明
- 画像ファイル名も意味のある名前にする
- 画像のサイズや圧縮も最適化する
これらを意識するだけで、検索エンジンが画像の内容を正しく理解し、検索結果に反映しやすくなります。
アクセシビリティを考慮した使い方
アクセシビリティとは、誰でも情報にアクセスしやすくすることです。
特に視覚に障がいのある人にとって、画像が何かを説明する方法はとても大切です。
figureタグとその中のimgやfigcaptionを正しく使えば、画面読み上げソフトなどにも正しく情報が伝わります。
アクセシビリティを高めるためのポイントは次の通りです。
- imgには必ずalt属性をつける
- figcaptionで画像の文脈を補足する
- キャプションは明確で簡潔にする
- 文章とのつながりがわかるようにする
- デザインだけの画像にはaltを空にする
このような工夫をすることで、誰にでもやさしいWebページが作れるようになります。
画像ギャラリーにおけるfigureの使用例
画像ギャラリーを作るときにも、figureタグはとても役に立ちます。
1枚1枚の画像に対して説明をつけることで、見ている人がその画像の意味や背景をしっかり理解できます。
ギャラリーの中でのfigureの使い方を知ると、よりプロらしいHTMLが書けるようになります。
ギャラリーでの活用例を紹介します。
- それぞれの画像を個別のfigureタグで囲う
- figcaptionで画像の名前や場所などを説明
- CSSでグリッド表示にすれば見栄えが良くなる
- モバイル対応にすることで見やすさがアップ
- 画像にリンクをつけることで詳細ページへ誘導可能
このように、ギャラリー形式でfigureを使うことで、視覚的にも情報的にも優れたページを作ることができます。
レスポンシブ画像とfigureタグの関係
今の時代、パソコンだけでなくスマートフォンやタブレットでもWebを見るのが当たり前です。
そこで必要なのが、画面の大きさに応じて画像を柔軟に表示できるレスポンシブ画像です。
figureタグと組み合わせることで、レスポンシブなデザインでも意味のある画像表現ができます。
以下にポイントを紹介します。
- <picture>タグとimgを組み合わせる
- media属性で画面サイズごとに画像を切り替える
- figureで全体を囲って意味づけする
- figcaptionでどの画面サイズでも説明を表示
- CSSで画像の幅を100%に設定する
このように、figureタグはレスポンシブ対応の補助としてもとても便利なタグなのです。
画像の意味を明確にするマークアップ手法
Webページの中で画像をただ見せるだけでなく、その画像がなぜ必要なのかを伝えることが大切です。
意味のあるマークアップをすれば、読み手にも検索エンジンにも内容がしっかり伝わります。
意味を明確にするためのコツは次の通りです。
- figureタグで情報のまとまりを作る
- figcaptionで画像の目的を伝える
- alt属性は画像の内容を簡潔に説明
- 画像のそばに関連するテキストを置く
- 画像の文脈を無視しない配置にする
これらを意識すれば、画像がただの飾りではなく、しっかりと情報の一部として機能するようになります。
SEO対策としてのfigureタグの活用方法

Googleはfigureタグをどのように評価するか
Googleは、HTMLの構造を見てページの内容を理解しようとします。
つまり、意味のあるマークアップ(セマンティックなタグ)を使っていると、検索エンジンに対して「この情報はこういう意味があります」と伝えやすくなるのです。
figureタグは、画像や図が「本文の一部だけど独立した情報」であることを示すためのタグなので、Googleにもその意図が伝わりやすくなります。
評価されるポイントは以下の通りです。
- 意味のある画像構造になっている
- figcaptionで説明されている
- 本文と画像の関連性がわかる
- アクセシビリティが確保されている
- HTML構造が明確で読み取りやすい
このように、figureタグを使うことでGoogleの評価が高まり、検索順位の向上につながる可能性があります。
画像検索結果に強くなるHTML構造
Google画像検索で上位に表示されるためには、画像そのものだけでなく、画像のまわりのHTML構造がとても重要です。
figureタグを使ったマークアップは、その構造を整えるのに最適な方法のひとつです。
画像検索で強くなるポイントをまとめます。
- figureタグで画像とキャプションを囲む
- imgタグには正確なalt属性をつける
- 画像ファイル名も内容に合ったものにする
- figcaptionには画像の意味を簡潔に書く
- 周囲のテキストと画像が関連している
このように、HTMLの構造を工夫するだけで、画像検索のパフォーマンスを大きく上げることができます。
alt属性とfigcaptionの最適な書き方
alt属性とfigcaptionは、画像の内容や意味を補足するためにとても大切です。
正しく使えば、SEOにもアクセシビリティにも効果があります。
しかし、間違った書き方をすると逆効果になることもあるので注意が必要です。
ここでは、それぞれの最適な書き方を紹介します。
- alt属性:画像の内容を短く明確に表現
- alt属性:装飾画像には空のalt(alt=””)を使う
- figcaption:画像の背景や補足情報を説明
- figcaption:文章として自然な形にする
- 両方が同じ内容にならないようにする
このように、alt属性とfigcaptionを適切に使い分けることで、ユーザーにも検索エンジンにも画像の意味がしっかり伝わります。
構造化データとfigureタグの関係
構造化データとは、Googleなどの検索エンジンに「この情報はこういう意味です」と伝えるための仕組みです。
たとえば、レビュー、レシピ、イベントなどの情報を専用のマークアップでタグ付けすることで、検索結果にリッチな表示をさせることができます。
figureタグはこの構造化データの補完的な役割も果たします。
組み合わせるポイントは以下の通りです。
- schema.orgのImageObjectと一緒に使う
- figcaptionで内容を補足する
- 画像のURLや説明文を明記する
- title属性などと合わせて使う
- HTML全体の意味を統一させる
このように、構造化データとfigureタグをうまく連携させることで、検索結果で目立ちやすくなるメリットがあります。
表示速度への影響と最適化のポイント
画像はWebページの中でも特に読み込み時間がかかりやすい要素です。
いくらfigureタグでSEOを意識したとしても、画像の読み込みが遅ければ検索順位に悪影響を与えることもあります。
そのため、表示速度の最適化もとても大事です。
対策のポイントを以下にまとめます。
- 画像のファイルサイズをできるだけ小さくする
- WebPなどの軽量フォーマットを使う
- Lazy Load(遅延読み込み)を活用する
- CDNを使って画像を高速配信する
- 画像の表示サイズと実サイズを合わせる
これらの対策を行えば、見た目とSEOの両方を高めながらページを高速に表示できます。
画像コンテンツの内容理解を高める方法
画像は文章よりも直感的に情報を伝えられる反面、その意味や背景は見る人によって違って見えることがあります。
だからこそ、画像の内容をしっかり伝えるための工夫が必要です。
figureタグはその助けになります。
画像の理解を高める工夫としては次の通りです。
- 画像の前後に説明文を入れる
- figcaptionで内容や背景を具体的に書く
- 関連する文章の近くに画像を配置する
- 複数画像の場合は流れがわかる順に並べる
- テキストと画像の意味がずれないようにする
こうした工夫をすることで、画像が単なるビジュアルではなく、しっかりと「伝わる情報」になります。
CMSでのfigureタグ実装時の注意点
CMS(コンテンツ管理システム)を使っていると、自動的に生成されるHTMLにfigureタグを加えるのが難しいこともあります。
しかし、正しく実装することでSEOやアクセシビリティの面でも大きな効果があるため、導入方法を理解しておくことが大切です。
注意するポイントを紹介します。
- テーマやテンプレートのHTML構造を確認する
- 画像アップロード時にalt属性を設定できるようにする
- figcaptionを使えるエディタかチェックする
- プラグインでfigure対応する方法もある
- 出力HTMLを確認してタグ構成を調整する
このように、CMSでもきちんと対応すれば、見た目も機能も優れた画像コンテンツを作ることができます。
figureタグの使用でよくあるミスと正しい対処法
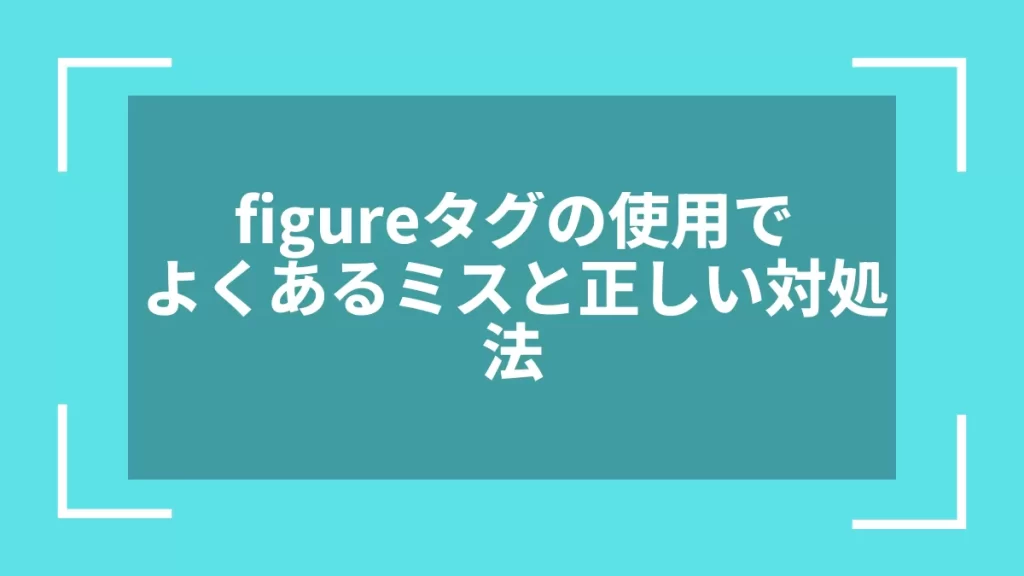
figcaptionの配置ミスと修正方法
figcaptionの位置を間違えてしまうと、ブラウザや読み上げソフトで正しく表示・読み取られないことがあります。
figcaptionは必ずfigureタグの中に配置する必要があります。
また、imgタグの前でも後でもOKですが、文脈に合った自然な位置に置くのが大切です。
よくある配置ミスとその修正方法をまとめます。
- figureの外にfigcaptionを置いてしまう → figureタグの内側に移動する
- figcaptionを複数入れてしまう → 1つのfigureには1つのfigcaptionにする
- タグの順序が不自然 → 読みやすい順番(img→figcaption)にする
このように、正しい位置にfigcaptionを置くだけで、意味の通るHTMLが完成します。
タグのネスト構造の誤り
HTMLは、タグの入れ子(ネスト)構造が正しくないと、ページの表示や意味が崩れてしまいます。
figureタグの中に、imgやfigcaptionなどを入れるときも、必ずタグが正しく閉じられているか確認する必要があります。
ネストでよくあるミスとその直し方は以下の通りです。
- imgタグを閉じ忘れる → <img />の形にする
- figcaptionがfigureの外に出ている → figureの中に戻す
- figureタグの閉じタグが抜けている → </figure>を追加する
正しいネスト構造にすることで、ブラウザや検索エンジンに意図した意味がきちんと伝わります。
CSSでの見た目調整ミス
CSSを使ってfigureやfigcaptionのデザインを整えるときにも、間違った書き方をすると表示が崩れたり、意味が伝わりにくくなることがあります。
特にfigcaptionを非表示にしてしまったり、意図しない場所に動かしてしまうケースが多く見られます。
見た目調整でのミス例と注意点を紹介します。
- figcaptionにdisplay:noneを使って隠してしまう
- position:absoluteでキャプションが見えなくなる
- 画像に対してfigcaptionの余白が不足
- レスポンシブ時にレイアウトが崩れる
- CSSでfigureの意味を壊してしまう
これらのポイントを意識することで、デザインも見やすく、情報もきちんと伝わるページに仕上がります。
アクセシビリティを無視した設計
figureタグは意味を持つタグですから、視覚に障がいのある人にも伝わるように工夫する必要があります。
たとえば、figcaptionで説明しているつもりでも、alt属性を省略してしまっていると、スクリーンリーダーで画像の意味がわからなくなってしまいます。
アクセシビリティを高めるためには、次のような点に注意します。
- imgタグにはalt属性を必ず設定
- figcaptionには画像の補足情報を簡潔に記述
- コントラストを意識した文字色にする
- キーボード操作でも読みやすい構造にする
- 意味のある画像だけにfigureを使う
アクセシビリティに配慮したマークアップは、すべての人にとって見やすく、使いやすいWebを作る第一歩です。
SEOを意識しすぎた不自然な記述
SEOを意識しすぎるあまりに、画像やfigcaptionに不自然なキーワードを詰め込みすぎてしまうケースがあります。
Googleはそうしたテクニックをすぐに見抜き、逆に評価を下げてしまうこともあります。
避けたい不自然な書き方の例を紹介します。
- figcaptionにキーワードを何度も繰り返す
- alt属性に長すぎる文章を入れる
- 内容と関係ないキーワードを入れる
- 意味があいまいなキャプションを書く
- 自然な言葉ではなくロボット向けの文章にする
SEOは大切ですが、本当に大事なのは「人にとって読みやすい文章」であることです。
ブラウザによる表示差異への対処
figureタグやfigcaptionは、どのブラウザでも基本的に同じように動作しますが、古いブラウザや一部のモバイル端末では表示が崩れることがあります。
そのため、事前にいろいろな端末やブラウザで表示確認をしておくことが重要です。
表示差異を減らすための工夫を紹介します。
- CSSリセットを使って各ブラウザの初期設定を統一
- レスポンシブデザインで表示を調整
- figcaptionの文字サイズや配置に注意する
- ブラウザごとのレンダリングの違いを確認
- 検証ツールでデバッグする習慣をつける
このような対策を取ることで、どんな環境でも正しく見えるWebページが作れます。
マークアップのバリデーションエラー対策
HTMLは正しくマークアップしないと、エラーが出たり、検索エンジンに正しく評価されないことがあります。
特にfigureやfigcaptionなどの新しいタグを使うときは、HTML5に対応しているか、構文が正しいかを必ず確認しましょう。
バリデーションエラーを防ぐ方法をまとめます。
- 閉じタグを忘れずに記述する
- タグの入れ子が正しいかチェック
- 不要な属性を削除する
- W3Cのバリデータで確認する
- DOCTYPE宣言がHTML5になっているか確認
これらを守ることで、エラーのないきれいなコードとなり、信頼性の高いページを作ることができます。
まとめ

これまでに紹介してきた内容をふまえて、figureタグを使うときに大切なポイントを振り返りましょう。
- figureタグは画像や図に意味を持たせるためのHTMLタグ
- figcaptionで画像に説明文をつけると内容が伝わりやすくなる
- imgタグと一緒に正しく使うことでSEOに効果が出る
- alt属性や構造化データで検索エンジンに情報を伝えやすくする
- アクセシビリティに配慮してすべての人に優しいマークアップにする
- CSSやCMSでも正しく表示されるように工夫する
今日学んだ使い方を自分のWebページでも試して、よりわかりやすくて伝わるサイト作りに役立ててみてください。

















