Webサイトを作っていると、「articleってどこで使えばいいの?」って迷うことありますよね。
似たタグがいくつもあって、何となく使ってるけど本当の意味はよくわからない、そんなふうに感じている方も多いと思います。
今回は、HTMLタグの中でも特に大事なarticleタグの意味と正しい使い方について、わかりやすく説明していきます。
articleタグの本当の使い方がわかれば、Webページの構造がきれいに整理できるようになり、検索エンジンにもユーザーにも伝わりやすいサイト作りができるようになりますので、ぜひ最後まで読んで参考にしてください。
articleタグとは何か?基本的な意味と役割を解説
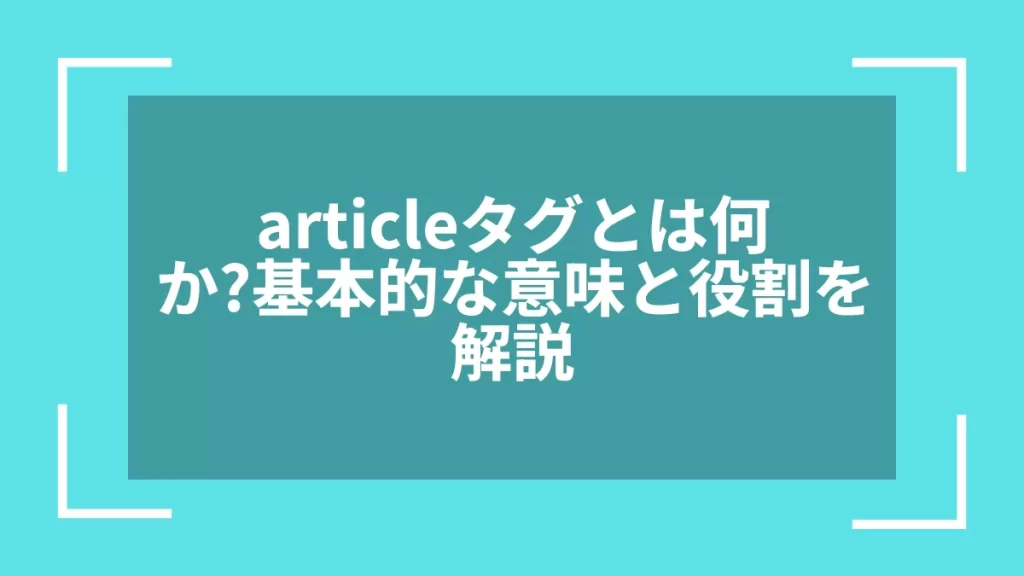
HTMLにおけるarticleタグの定義
HTMLのarticleタグは、独立した内容のまとまりを表すためのタグです。
たとえば、ブログ記事やニュース記事、商品レビューなど、それ単体でも意味が通じる内容に使います。
これは、ただの段落やタイトルではなく、コンテンツのひとつのかたまりとして扱われることがポイントです。
articleタグは、次のようなときに使われます。
- ブログの投稿記事
- ニュースサイトの記事
- 掲示板の投稿
- レビューや口コミの内容
- マガジンやコラムの各章
このように、それぞれの記事や投稿が独立していて、他のページでもそのまま読めるという特徴があります。
HTMLの中でも、情報のかたまりをしっかり区切って見せたいときに便利なタグです。
articleタグの目的と利用シーン
articleタグは、「これはひとつの完成された情報です」とブラウザや検索エンジンに伝えるために使います。
たとえば、ニュースサイトでは、ページの中にいくつかの記事が並んでいますが、その1つ1つにarticleタグを使うことで、「ここからここまでが1記事です」と示すことができます。
よく使われるシーンを簡単にまとめると、以下のようになります。
- ニュースサイトでの1つの記事
- ブログの1投稿
- Q&Aサイトでの質問と回答
- 商品レビューサイトでの各レビュー
- メールマガジンでの各コンテンツブロック
articleタグを使うことで、検索エンジンが内容を理解しやすくなり、SEOにもプラスになります。
それに、ページの構造もわかりやすくなり、読みやすくて使いやすいWebサイトになります。
articleタグとsectionタグの違い
articleタグとsectionタグは、どちらもHTMLの中でコンテンツをグループ化するタグですが、役割は少し違います。
混同しやすいので、しっかり区別しましょう。
ここで、両者の違いを整理してみます。
- article:それ単体で意味が通じる内容
- section:全体の中の一部、トピックの区切り
- article:記事、レビュー、投稿など
- section:章、セクション、話題の区分け
- article:外部にも出せる
- section:内部構造を整理する目的
このように、articleは「完成された情報」、sectionは「話の区切り」という違いを理解しておくと、使い分けがとてもラクになります。
articleタグに含めるべき要素とは
articleタグの中には、その記事を理解するために必要な要素を入れるのが基本です。
ただ文章だけでなく、タイトル・本文・著者・日付なども含めることで、より意味のある構造になります。
代表的な要素を以下にまとめます。
h1~h3:見出しp:本文の段落time:公開日時footer:記事の情報(著者など)figure:画像などの図
これらをうまく組み合わせることで、検索エンジンにもユーザーにもやさしい記事構造になります。
W3CとWHATWGにおける仕様の違い
HTMLの仕様には、W3C(World Wide Web Consortium)とWHATWG(Web Hypertext Application Technology Working Group)という2つの団体があります。
どちらもHTMLの標準化を行っていますが、articleタグに関しては、大きな違いはありません。
ただし、それぞれの定義の細かさには少し違いがあります。
- W3Cは厳密な構造と意味を重視
- WHATWGは柔軟性や実装優先の姿勢
- 両者とも
articleは「独立した内容のまとまり」と定義 - 使い方に迷ったときはWHATWGの方が実用的
- ブラウザ実装はWHATWGに近いことが多い
どちらの仕様でも、articleは自立した情報の単位として認識されています。
つまり、使い方は大きく変わらないので、基本をおさえていれば問題なく使えます。
他のHTMLタグとの使い分け方
HTMLにはたくさんのタグがあるので、articleタグの使いどころに迷うこともあります。
他のタグとの違いを理解して、正しく使い分けることが大切です。
次のようなタグとよく比較されます。
div:ただの箱。意味を持たせたいならarticlesection:話題の区切り。独立性があるならarticleaside:補足情報。本文と関係が薄いならasidemain:ページの主な内容。複数記事ならarticleを内包header/footer:記事の上下情報。articleにも使える
これらを正しく使い分けることで、HTMLの構造がぐっとわかりやすく、検索にも強くなります。
タグの意味を知って、ただの見た目だけで使うのをやめましょう。
articleタグの正しい使い方と実装例
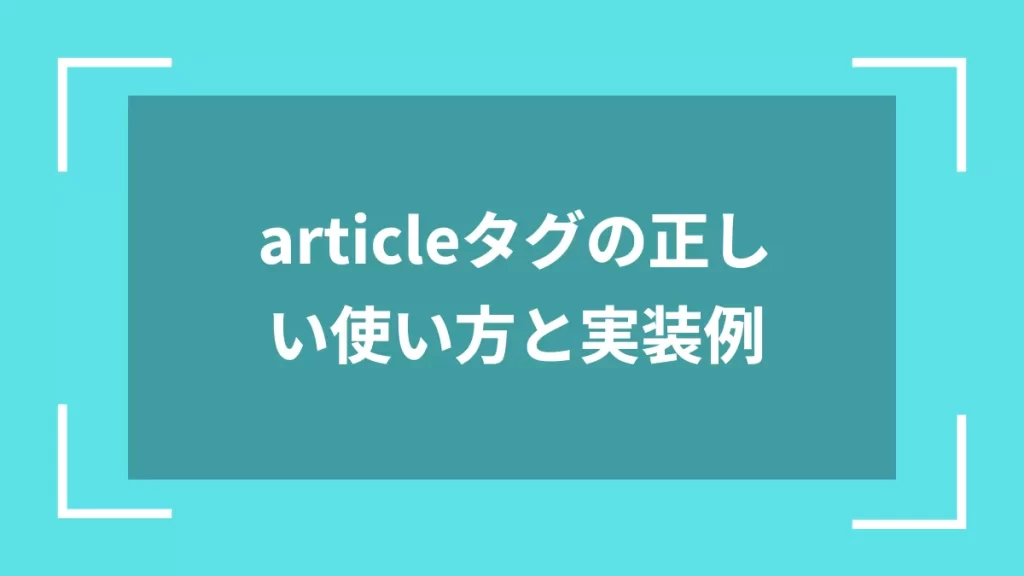
基本的な構文と記述方法
articleタグの使い方はとてもシンプルですが、正しい構文を知っておくことが大切です。
このタグはHTML5から導入されたもので、以下のような基本構造で使います。
<article>
<h2>記事のタイトル</h2>
<p>記事の本文内容</p>
<footer>投稿者情報や投稿日など</footer>
</article>
ここでは、<h2>が見出し、<p>が本文、<footer>はその記事に関する補足情報になります。
このように、1つの記事として完結した内容を囲むのがarticleタグの特徴です。
見出しタグ(h1〜h3)との組み合わせ方
articleタグの中に見出しタグを使うときは、構造にあわせて正しい順番で使うことがポイントです。
見出しはページ全体の中で階層的に扱われるので、h1からh3などをうまく使い分けましょう。
見出しタグの使い方は次のようになります。
- ページ全体のタイトルには
h1 - 各
articleのタイトルにはh2やh3 - 記事の中のセクションに
h3やh4を使う articleごとに見出し階層はリセットされる- 意味のある順番で見出しを使うことが大事
見出しタグの順番がバラバラだと、検索エンジンや読み上げソフトが内容を正しく理解できません。
読み手にも伝わりやすい構成を心がけることが重要です。
複数記事がある場合の使い方
1つのページの中にいくつかの記事を表示したい場合は、それぞれをarticleタグで囲むことで、内容をきれいに分けることができます。
たとえば、ブログの一覧ページやニュースのトップページなどがこのケースに当たります。
このときの構成例は以下のようになります。
<article>
<h2>記事1のタイトル</h2>
<p>記事1の内容</p>
</article>
<article>
<h2>記事2のタイトル</h2>
<p>記事2の内容</p>
</article>
このようにarticleを複数使うことで、それぞれの記事が意味を持って独立していることを伝えられます。
また、検索エンジンにも伝わりやすくなり、SEO対策にも効果があります。
入れ子構造にしてもいいのか?
articleタグは、入れ子(ネスト)にして使うことも可能です。
たとえば、ある記事の中に別の記事への紹介やレビューが含まれているようなケースでは、内部にもarticleを入れて問題ありません。
使い方の例としては、次のようなものがあります。
- 元記事の中で、関連する記事を紹介する場合
- レビュー記事内にユーザーの感想を複数含めたい場合
- まとめ記事内で、個別記事を並べたいとき
ただし、入れ子が深くなりすぎると構造が複雑になり、読み手にとってわかりにくくなる可能性があります。
入れ子を使うときは、本当に必要な場合に限って慎重に使うことが大切です。
ブログやニュースサイトでの実装例
実際にブログやニュースサイトでは、articleタグがとてもよく使われています。
これにより、各記事がそれぞれ独立して表示され、デザインやSEOの両面でメリットがあります。
ここでは、よくある使い方を紹介します。
- トップページに記事一覧を表示するとき
- 各記事ページの本文を囲むとき
- サイドバーにおすすめ記事を表示するとき
- カテゴリー別に記事をまとめたいとき
- ニュースサイトで速報や特集を分けて表示するとき
こうした実装では、articleタグとheaderやfooter、sectionなどを組み合わせて使うことで、ページ全体の構造がしっかり整理されます。
結果的に、読みやすく、検索にも強いページ作りが可能になるのです。
マークアップミスを防ぐためのポイント
articleタグを使う際にありがちなミスを避けるには、いくつかのポイントを守ることが重要です。
正しいマークアップは、表示の崩れやSEO評価の低下を防ぐことにつながります。
ミスを防ぐための注意点を紹介します。
- ただの装飾目的でarticleを使わない
- 1つの記事に1つのarticleを使う
- 入れ子が深くなりすぎないようにする
- 見出しタグの順番を守る
- 必要な情報をarticle内にまとめる
これらを意識しておくと、わかりやすく整ったHTMLを書くことができ、ユーザーにも優しい設計になります。
1つ1つ丁寧にマークアップすることが大切です。
articleタグ使用時の注意点とよくある間違い
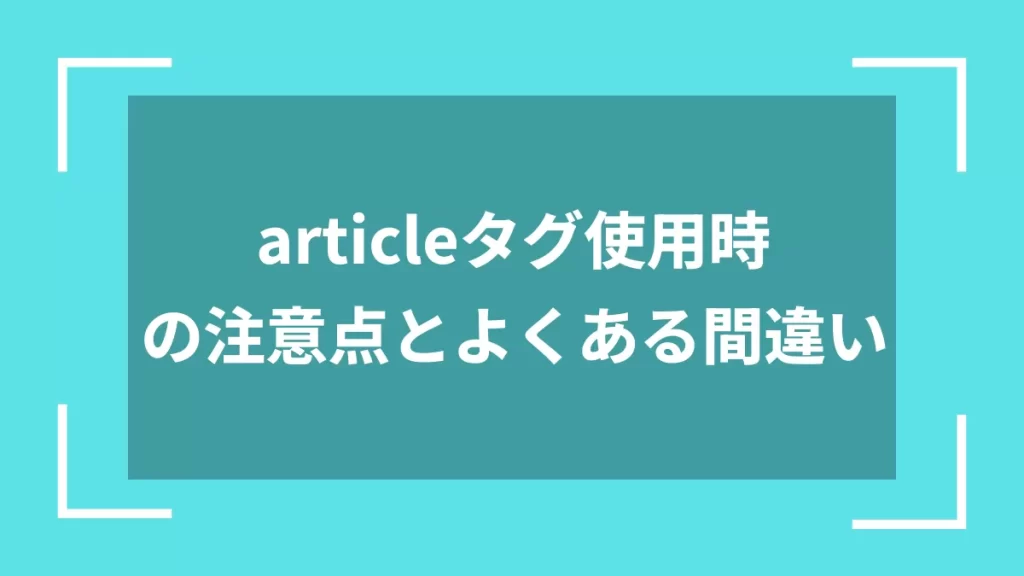
意味を持たない装飾目的の使用
articleタグは見た目を変えるためのタグではありません。
ですが、よくある間違いのひとつに、「ただのレイアウトのため」にarticleを使ってしまうケースがあります。
これは検索エンジンやユーザーにとって意味のないマークアップとなってしまいます。
このような間違いを避けるためには、次のようなポイントに注意しましょう。
- デザイン目的なら
divを使う articleは独立した意味を持つ内容に使う- 見た目ではなく内容の意味でタグを選ぶ
- CSSのスタイル指定はタグの役割と無関係にできる
- 装飾と構造を混同しないことが大切
これらを意識することで、意味のあるHTMLマークアップができ、SEOにも良い影響を与えるようになります。
articleタグの乱用による構造の混乱
articleタグは便利なタグですが、使いすぎるとかえってページの構造が分かりにくくなる場合があります。
特に、1ページの中に何十個ものarticleがあると、読み手も検索エンジンも混乱してしまいます。
使い方のバランスを取るためには、以下のような工夫が必要です。
- 意味のある情報のまとまりだけに使う
- 1記事に1つの
articleを原則とする - 構造を簡潔にする
- 不要な繰り返しを避ける
- データや画像の表示には
articleを使わない
articleタグは「使えば使うほど良い」というものではありません。
使う場所と回数を見極めることが重要です。
SEO目的だけで使用する危険性
検索で上位に表示させたいという思いから、articleタグを多用する人がいますが、それは逆効果になる可能性もあります。
検索エンジンはHTMLの意味を読み取ってページの内容を判断します。
意味のないarticleが多いと、信頼性が下がってしまうこともあるのです。
正しいSEO対策としては、次のような考え方が大切です。
- 意味を持つ記事にだけ使う
- 装飾のためには使わない
- HTMLの構造を整えることを優先
- ユーザーにとって読みやすい形を意識
- タグの意味を理解して使う
タグは見せかけの道具ではありません。
正しく使うことで、SEOにも自然と良い効果が出てくるのです。
アクセシビリティの観点での注意点
articleタグを使うときには、アクセシビリティ(すべての人が使いやすい設計)も意識する必要があります。
たとえば、視覚に障害のある人が使う読み上げソフトは、articleの中身を読み上げます。
そのため、わかりやすい構造と正しい見出しの順番がとても大切になります。
気をつけるポイントをまとめると、次のようになります。
articleの中には必ず見出しを入れる- 記事ごとに内容を区切ってマークアップする
aria-labelなどの属性も活用する- 読み上げやすい順番で要素を並べる
- 説明が必要な要素には代替テキストを付ける
このように、HTMLは見た目だけではなく、誰にとっても使いやすく設計することが求められます。
CMSで自動生成されるマークアップの確認
WordPressや他のCMS(コンテンツ管理システム)では、記事を投稿するだけで自動的にarticleタグが使われることがあります。
そのため、自分で何も書かなくてもarticleが出力されている場合も多いです。
しかし、それが正しく機能しているかを確認することがとても重要です。
自動生成に頼りすぎると、以下のような問題が起こることがあります。
- 不要な
articleが大量に出てくる - 階層構造が崩れる
- 必要な情報が
articleに入っていない - 見出しが欠けている
- 重複するIDやクラスの混在
CMS任せにせず、HTMLの出力を確認し、自分の意図通りの構造になっているかをしっかり見直すことが、きれいなWebページを作るコツです。
sectionタグと混同するケース
articleとsectionはとても似ているので、どっちを使えばいいのか迷う人も多いです。
ですが、この2つは役割が違います。
articleは独立したコンテンツ、sectionは話のまとまりや章を表します。
違いをわかりやすくするために、次のような使い分け方を意識しましょう。
article:ブログ記事、ニュース、レビューなどsection:目次、話題の切り替え、章立てarticle:それだけで意味が通じる内容section:他の要素と組み合わせて意味が完成article:単体でも独立した情報として使える
このように、どちらも大事なタグですが、目的が違います。
意味をよく考えて使い分けることで、読みやすく整理されたHTML構造が実現できます。
HTMLバリデーションでのエラー回避
articleタグを正しく使っていても、うっかりした書き間違いでエラーが出てしまうことがあります。
こういったエラーは検索エンジンにも影響を与える可能性があるので、バリデーションツールで確認することがとても大切です。
エラーを防ぐために注意すべきポイントをまとめます。
- 開始タグと終了タグを必ずセットで書く
- タグの入れ子を正しくする
- 不要なタグを入れない
- 属性の記述ミスを避ける
- W3CのHTML検証ツールを使って確認する
バリデーションは自分の書いたHTMLにミスがないかを調べるための道具です。
こまめに使って、正しくてきれいなHTMLを書く習慣をつけることが大切です。
articleタグとSEOの関係性と最適化のコツ
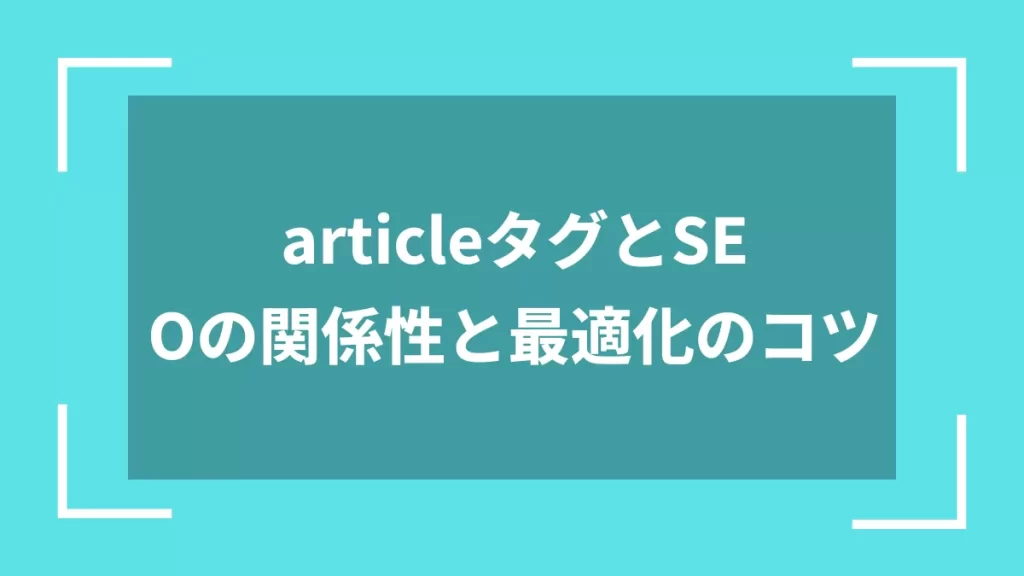
検索エンジンがarticleタグをどう評価するか
articleタグは、検索エンジンにとって「この部分は独立した重要なコンテンツです」と伝えるための重要な目印になります。
つまり、Googleなどの検索エンジンはarticleタグの中身をひとつの記事として評価しようとします。
そのため、正しい使い方をしていれば、インデックス(検索結果に載る)されやすくなり、SEOに効果的です。
では、検索エンジンが注目するポイントを紹介します。
article内にしっかりとした構成があるか- 見出しタグ(
h2など)が含まれているか - 本文のテキストが豊富にあるか
- 重複コンテンツになっていないか
- 記事ごとに独立した情報として価値があるか
これらの点をクリアしていれば、articleは検索エンジンにとってとても意味のある要素となります。
正しく使えばSEOに有利なタグになるのです。
構造化データとの併用方法
articleタグを使うときに、さらにSEO効果を高めたいなら構造化データ(JSON-LDなど)と一緒に使うことをおすすめします。
これは、検索エンジンに「この記事はニュースです」「この情報はレシピです」などと具体的に伝えるためのコードです。
たとえば、ニュース記事の場合はこんなふうに記述します。
<script type="application/ld+json">
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"headline": "タイトル",
"datePublished": "2025-04-15",
"author": {
"@type": "Person",
"name": "著者名"
}
}
</script>
構造化データを使うと、次のような利点があります。
- 検索結果に画像や日付が表示されやすくなる
- クリック率が上がる可能性がある
- 情報が明確に伝わるため、信頼性が上がる
- リッチリザルト(目立つ表示)に対応しやすくなる
- Google Discoverなどに載りやすくなる
このように、articleタグと構造化データを組み合わせることで、検索エンジンへのアピール力を高めることができます。
Google検索結果における影響
Googleの検索結果において、articleタグの使い方はクリック率や表示内容に影響を与える可能性があります。
Googleはページの中でどの部分が重要かを判断する際に、articleタグをヒントのひとつとして使います。
実際、Googleが公式に提供している「構造化データのガイドライン」でも、articleタグはニュース、ブログ、技術文書などに使うことが推奨されています。
Google検索での影響を受けやすいポイントは次のとおりです。
- 検索結果に表示されるタイトルや説明文の精度
- リッチリザルト対応の可否
- Googleニュースへの掲載可能性
- 記事の内容とキーワードの一致度
- インデックスまでのスピード
このような要素に関わってくるため、articleタグはただの見た目ではなく、SEOの重要な要素と言えるのです。
見出しとarticleタグの最適な組み合わせ
articleタグと見出しタグ(h1~h3)はセットで使うことで、検索エンジンにもユーザーにも内容が伝わりやすくなります。
適切な見出しをつけることで、そのarticleがどんな話をしているのかがはっきりするのです。
見出しとの組み合わせで気をつけたいポイントを挙げます。
article内には必ず1つの見出しを入れる- ページ全体では
h1は1つだけにする h2やh3を使って内容を段階的に整理する- 見出しと本文の内容が一致するようにする
- キーワードを含んだ自然なタイトルにする
これを守ることで、articleの内容がより検索に引っかかりやすくなり、訪問者にも読みやすくなります。
インデックスされやすい構造とは
articleタグを正しく使うことで、Googleのインデックスにも入りやすくなります。
インデックスとは、検索エンジンのデータベースに「このページがあるよ」と登録されることです。
これがされないと検索結果には出てきません。
インデックスされやすい構造には、次のような特徴があります。
- 見出し、本文、著者、日時などの情報がそろっている
- 構造化データが含まれている
- 画像に代替テキストがある
- ページの表示速度が速い
- モバイル対応がされている
articleタグを使って情報をきちんとまとめることで、Googleがページを認識しやすくなり、素早くインデックスされやすくなるのです。
モバイルファーストでの活用ポイント
最近では、Googleはモバイル向けの表示をもとにページを評価しています。
これをモバイルファーストインデックスといいます。
そのため、スマホでも見やすく、読みやすいarticleの使い方がとても大切になります。
モバイルでの使い方のコツをまとめてみましょう。
- 1つの
articleの情報量を適切にする - 行間を広めにして読みやすくする
- 画像がスマホでも表示崩れしないようにする
- 見出しの文字サイズを調整する
- タップしやすいレイアウトにする
こうした工夫をすることで、モバイルでも読みやすくなり、SEOの評価も高まりやすくなります。
実際のサイトでのSEO成功事例に見るポイント
多くの成功しているブログやニュースサイトでは、articleタグを正しく使っています。
それだけでなく、記事の構造を明確にし、検索エンジンとユーザーの両方にわかりやすく設計しているのです。
成功しているサイトに共通するポイントを紹介します。
articleごとに見出しと本文が明確- 構造化データで情報を強調
- モバイルでも快適に読める設計
- 記事の中身が深くて独自性がある
- 装飾よりも内容と構造を重視している
こういった点を取り入れていけば、自分のサイトでもarticleを使ったSEOが成功する可能性が高くなります。
正しい使い方を実践することが、上位表示への第一歩です。
まとめ
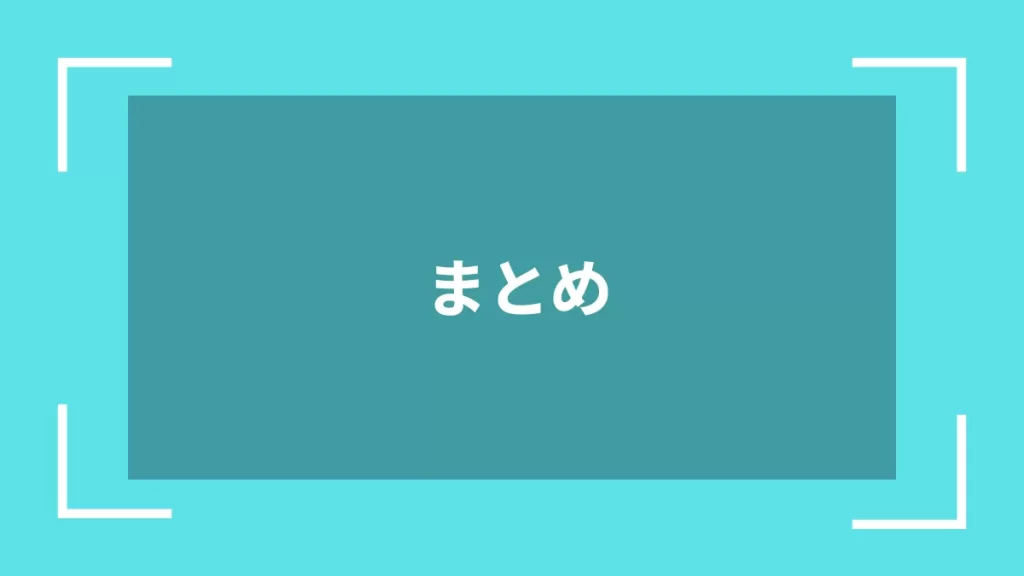
これまで、articleタグの意味や正しい使い方、よくある間違い、SEOとの関係まで詳しく説明してきました。
ここで、特に大事なポイントをまとめます。
- articleは独立した情報のまとまりに使う
- 見た目のために使うのはNG
- sectionタグやdivタグと役割を区別する
- 構造化データや見出しタグと一緒に使うと効果的
- SEOにもユーザーにもやさしい構造を作る
articleタグを正しく使えば、あなたのWebページはもっとわかりやすく、検索にも強くなります。
今日からぜひ、自分のサイトに取り入れてみましょう。

















